
岐阜・飛騨市
岐阜 ・ 飛騨市

引継ぎ実績あり
独自の
有限会社麺の清水屋
「飛騨で誇れる会社創り」のため、歴史を力に未来を創る
経営理念
飛騨で誇れる会社創り
代表者メッセージ
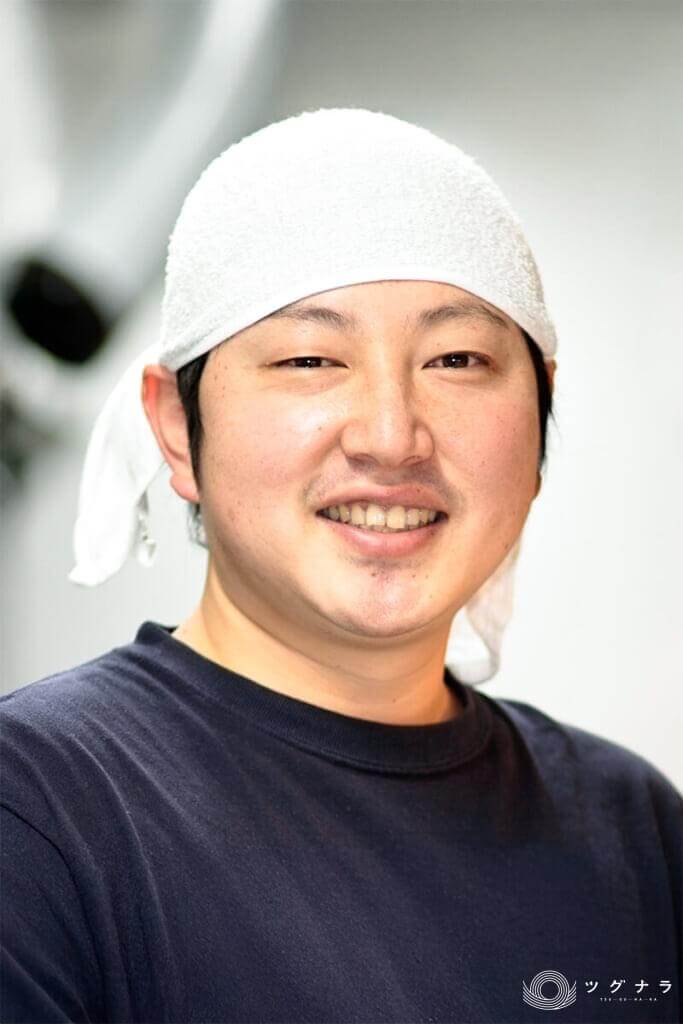
1948年の創業より、親子4代にわたって麺づくりに邁進してまいりました。 「安全、安心で、より美味しい麺づくり」のため、主原料である粉と水に徹底してこだわり、業務用の麺をはじめとする地元で永く愛される麺をお届けしています。
素材の吟味はもちろんのこと、万全の品質管理体制、そして麺ひとすじにかける深い愛情があります。そのすべては、一人でも多くのお客様に「食の感動」を味わっていただくという私たちの使命につながっています。
食の安全性が改めて問われる現代において、私たちはその責務をより一層重く受け止めております。
これからも社員一同、日々研鑽を重ね、日本の豊かな食文化の創造に貢献していきます。
代表取締役 清水 將行
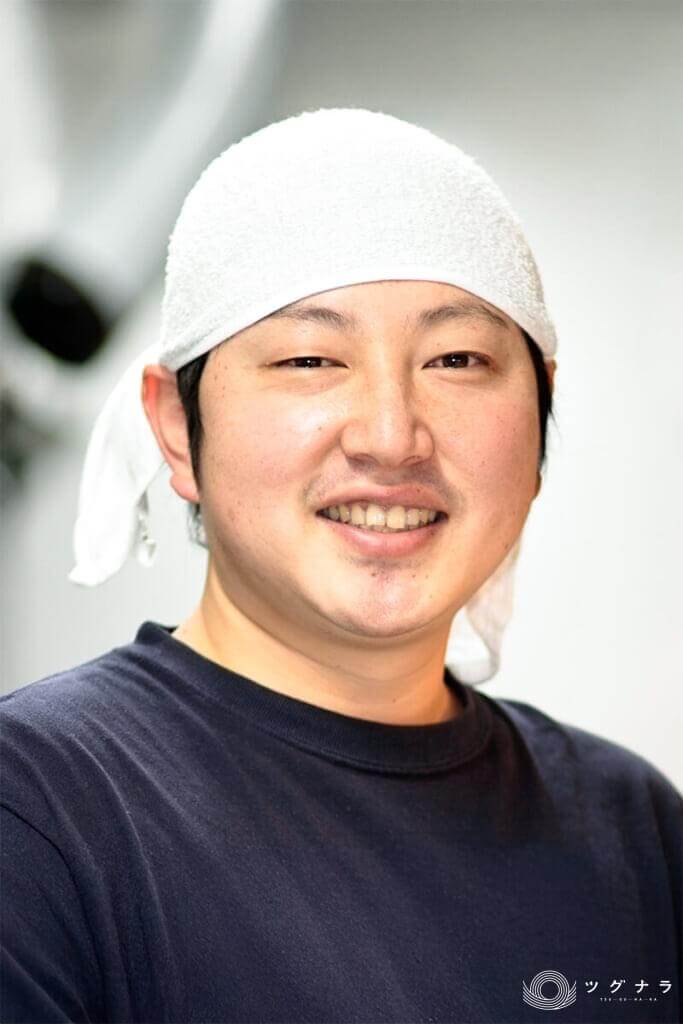
私たちのこだわり
「高山ラーメン」の食文化を育む
弊社は1948年、現在の岐阜県飛騨市神岡町で創業しました。創業者である私の曽祖父は、もともと材木商を営んでいましたが、戦後、深刻な食糧難と社会の変化を背景に「安価で保存が利き、手軽にお腹を満たせる主食こそ、今人々が求めているものだ」という想いを抱き、製麺業への転換を決断しました。
当初はうどんやそば、焼きそばなど多様な麺を手掛けており、順風満帆とは言えない苦しい時期も経験しました。
現会長である父の代に、会社は大きな転機を迎えます。全国的なラーメンブームが追い風となる中、父が着目したのは、この地に江戸時代から根づく「中華そば」の文化でした。
もともと飛騨では、大晦日に中華そばを「年越しラーメン」として食べる独自の文化が育まれていました。父は、この地域に眠る文化の価値をさらに高めようと、その特徴である細ちぢれ麺の製造に注力します。私たちの想いは、やがて地域の製麺所や飲食店をも巻き込む力となり、今日の「高山ラーメン」というブランドを確立するに至りました。
2013年頃からは、ラーメン製造に特化し、スーパーや小売店向けの商品を展開しています。さらに2020年には高山市の老舗ラーメン店「豆天狗」を事業承継し、飲食業への進出も果たしました。
そして、近年では、独自開発した「生麺長期保存技術」を足掛かりに、海外への本格的な輸出やECサイトの強化といった多角的な販路開拓を推進しています。時代の需要に応えながら、一人でも多くのお客様へ私たちの麺を届けたいと考えています。
おかげさまで袋麺事業は好調に推移し、会社全体の直近の売上高は4億2,380千円となりました。2025年度には売上5億円を目指しています。
売上の80%は卸売が占めており、そのうちの70%以上が飛騨地方と、地域に深く根ざした事業を展開しています。
家業を身近に感じて育ち、入社するまで
私の実家は弊社の工場の隣にあったため、会社を家のように感じながら育ちました。学校から帰ると、機械で製麺する様子を眺め、簡単な手伝いをして過ごしていたことを覚えています。また、いつも夜遅くまで働く父の姿を見るうちに、子どもながらにも「いつか兄か自分のどちらかが、この会社を継ぐのだろう」と考えるようになりました。
地元の高校を卒業後は、進学のために上京し、亜細亜大学に入学しました。大学時代は、学業の傍らバックパッカーとして世界20カ国以上を旅して回りました。その中で得た多様な文化や人々との出会いが、私の視野を大きく広げてくれました。そして、「自分も何かを成し遂げたい」「世界を舞台にビジネスをしたい」という、これまでになかった強い意欲が湧き上がってきたのです。ただ、それは家業を継ぐことなのか、あるいは自分で起業することなのかは漠然としていました。
しかし、帰国後に改めて家業を見つめ直したとき、ゼロから新しいものを生み出すことだけが挑戦ではないと考えました。「歴史あるこの会社を次のステージへ導くことこそ、やりがいのある挑戦ではないか」と思い至り、大学卒業後の2013年、弊社に入社しました。
全方位で改革を続け、挑戦が文化になる
入社後は、まず製造ラインで業務を一通り覚えたのち、営業も担当するようになりました。
当時、会社はちょうどラーメン製造に一本化した頃でしたが、実は債務超過という深刻な財務状況でもありました。売上高も現在の4分の1程度の約1億2千万円で、再生フェーズの真っ只中でした。経営に関しては全くの素人だった私ですが「なんとかしなければ」と、とにかく行動することから始めました。
まず「プライドを全部捨てる」と決め、以前から経営の支援をしていただいていたMMPCコンサルティンググループの先生や、地元の先輩経営者の方々に頭を下げて実践を学び、同時に、経営書を読み漁っては必死に理論を吸収しました。
そして、会社の根幹に関わる改革として、財務体制の見直し、営業活動、製造工程の効率化を行いながら、ワークフローの整理やマニュアル整備といった地道な内部改善にも一つひとつ取り組みました。自らの手で形にしていくしかなかったため、とても苦しい時期でした。
しかし、学んで実践すればするほど改善点が見つかり、すぐに成果が表れていくことに気がつき、大きなやりがいと面白さを感じるようになりました。
入社から3年もすると、一つひとつの取り組みが実を結び、会社の数字は確かな手応えとして表れ始めました。何より嬉しかったのは、社員の顔つきが日に日に明るくなっていくのが分かったことです。社内の雰囲気も好転し、売上が右肩上がりに伸びていく実感を社員全員と共有できたのは、何ものにも代えがたい貴重な経験でした。
そして、会社が軌道に乗り始めた2017年、父からの「会社を任せたい」という事業承継の打診を受けて、28歳で代表取締役社長に就任しました。
老舗ラーメン店「豆天狗」のM&A、「製販一体」のビジネスモデルへ
学生時代、ラーメン店巡りが趣味だった私には、「いつか自分の店を」という夢がありました。その想いを胸にしていた2020年、長年の大切な取引先であった地元の老舗ラーメン店「豆天狗」から「後継者がいない、引き継いでくれないか」という相談がありました。
もし引き継がずに豆天狗のブランドがなくなれば、コラボレーション商品などの関連商品の売上が失われるという経営上の懸念がありました。と同時に、もし事業を引き継いだら製麺所として自社の麺の価値を直接お客様に届けられる絶好の機会でもあると考えました。そして、「私たちの手でこのブランドを守り、育てよう」と事業承継を決意しました。
もともと豆天狗は家族経営でしたが、事業承継を機に退かれ、弊社の社員が運営を引き継ぐことになりました。弊社としては初めての飲食店経営でしたが、ブランドの味を守り、新しい挑戦に踏み出す社員を支える責任は、全て私にあると覚悟を決めました。
まずは私自らが先頭に立ち、社員たちとゼロから店づくりを始めました。
製麺事業の再生フェーズで培った、製造工程の標準化やマニュアル化といったノウハウを店舗運営にも応用し、味の再現やオペレーションなどスムーズに軌道にのせることができました。今ではインバウンドのお客様にも愛される人気店として、安定的に成長しています。
豆天狗の事業承継により弊社のビジネスモデルは「製販一体」へと昇華させることが出来ました。消費者の声を聞くことのできる機会が持てたことで、全ての社員がさらに「お客様の為に」という気持ちで物事を判断するようになりました。
変化を恐れない企業文化
私が社長に就任してからは、「飛騨で誇れる会社創り」という経営理念を新たに掲げました。 これは、単に製品の質が良いということだけでなく、働きやすさや企業としての品位、地域貢献といったあらゆる側面で、地域の人々に「この会社があってよかった」と誇りに思っていただけるような企業を目指す、という決意を込めています。そして何より、社員一人ひとりが「自分たちの会社は素晴らしい」と自信を持てる、そんな企業像を追求するものです。
この理念を浸透させるために、毎月の会議で必ず理念に立ち返る時間を作っています。会社が目指す方向性を繰り返し確認することで、社員全員が同じ想いを共有できるよう努めています。この理念の根底には、弊社に深く根付いている「変化を恐れない」という企業文化があります。
以前から在籍している社員は、会社が債務超過のどん底状態から再生していく過程を、身をもって知っていることもあり、「変わっていかなければ会社は成長できない」という共通認識が、新しく入った社員にも自然と浸透しています。
また、チームとしては、それぞれが得意分野で力を発揮する体制ができています。例えば、私の兄は経営の最前線に立つのではなく、総務や製造現場を支える「縁の下の力持ち」の役割を担ってくれています。このように、一人ひとりがそれぞれの力を発揮し、互いを補い合う文化が、会社全体の成長を支える大きな力になっています。
社員に任せる姿勢が未来を創造する
弊社の社員は20名ほどで、一人ひとりの顔が見える距離の近さが、強い信頼関係を育んでいます。社風も、「風通しが良く、オープンで協調的」と感じます。私自身、社長という立場に固執せず、社員との積極的な交流を大切にしています。例えば、自分から飲み会に参加して仕事以外の話をしたり、日頃から雑談を交わしたりと、できるだけフラットな関係性を築くことを心がけています。
素直で真面目な社員が多く、私の意見や会社の新しい方針を前向きに受け止め、実直に実行に移してくれます。特に、私より年上の中途採用の社員たちは経験豊富でありながらとても意欲的で、「若い社長に負けていられないな」と笑顔で話してくれる姿には、私が逆に大きな刺激とエネルギーをもらっています。
社員の教育・育成において、心がけているのは「権限移譲」です。新しい取り組みを始める際は、まず私が責任者としてある程度まで道筋をつけて形を作りますが、プロジェクトが軌道に乗ったと判断したら、すぐに担当者に権限を移譲し、完全に任せます。
日々の業務におけるほとんどの決定は社員に委ねており、私が最終判断を下すのは全体の1割程度に過ぎません。社員の当事者意識の向上に繋がり、自己成長意欲の高い組織になっています。
「生麺×長期保存」のブルーオーシャン市場で海外へ
現在、私たちが最も力を入れているのが海外展開です。麺類を輸出する場合、保存性の理由から乾麺が主流です。しかし、弊社の40年以上研究してきた技術力を活かせば「生麺」を提供できるのではないかと思いました。商品開発には時間もコストもかかりましたが、どうしても本来の日本ラーメンの美味しさを海外の方に届けたいと一切の妥協を許すことなく作り続けました。
高山ラーメンに最適なタンパク質量の多い特注小麦粉で「細さ・伸びにくさ・うまさ」の黄金比、さらにセラミック等で濾過した水を練りこむ等の独自の技術により、風味を一切損なうことなく生麺を常温で長期間保存できる、独自の「生麺長期保存技術」を確立することが出来ました。
約8年もの試行錯誤を経て完成したこのノウハウは、他社には決して真似のできない、私たちの誇りです。結果として、私たちは「生麺×長期保存」というブルーオーシャン市場を切り拓くことができたと自負しています。このこだわりと技術は、HACCP認定やSDGs宣言といった、社会的な信頼性によっても裏付けられています。
この「生麺×長期保存」を武器に本格的な海外展開へと進めています。現在は台湾、シンガポール、カナダなどへ展開し、まだ年商1,000万円規模ですが、将来の大きな柱として育てています。
地域に根ざしながら歩みを進める
創業80周年を見据え、私たちはこれからも「飛騨だからできる」ことを証明していきます。私たちは飛騨という小さな町から、挑戦し、成果を上げ、その価値を発信し続けていきます。
そのためにも、私たちが果たすべき役割は2つあると考えています。
一つは、地域資源「飛騨高山ラーメン」の魅力を国内外へ発信し、その文化を守り継ぐことです。
そしてもう一つは、過疎化が進むこの地だからこそ事業を成長させ、雇用の創出や地元とのコラボレーションといった形で地域に貢献し、ここに暮らす人々の誇りを育んでいくことです。
この使命を果たすため、私たちは「海外事業」と「ラーメン店事業」を両輪で力強く推進しています。海外事業では、「生麺で世界を席巻する」という大きな夢を、必ず達成すべき未来像として捉えています。現在は売上全体の約0.3%と黎明期ですが、アジアに加え、カナダやアメリカ、ヨーロッパへの展開も進め、数年内に会社全体で売上7億円規模への成長を見込んでいます。
一方、ラーメン店事業では、来る2025年8月に高山市に新店舗をオープンし、3店舗体制とします。最新の省力化設備を導入するこの新店舗をモデルケースとして、今後の多店舗展開やフランチャイズ化も見据えた運営体制を構築し、2030年には、ラーメン部門全体で年間売上1億5,000万円超を目指しています。
どんなに老舗企業になっても、気持ちは挑戦者です。常に「飛騨であることの誇り」を胸に、変革を創造し、飛騨の未来発展に貢献していきます。
「高山ラーメン」の食文化を育む
弊社は1948年、現在の岐阜県飛騨市神岡町で創業しました。創業者である私の曽祖父は、もともと材木商を営んでいましたが、戦後、深刻な食糧難と社会の変化を背景に「安価で保存が利き、手軽にお腹を満たせる主食こそ、今人々が求めているものだ」という想いを抱き、製麺業への転換を決断しました。
当初はうどんやそば、焼きそばなど多様な麺を手掛けており、順風満帆とは言えない苦しい時期も経験しました。
現会長である父の代に、会社は大きな転機を迎えます。全国的なラーメンブームが追い風となる中、父が着目したのは、この地に江戸時代から根づく「中華そば」の文化でした。
もともと飛騨では、大晦日に中華そばを「年越しラーメン」として食べる独自の文化が育まれていました。父は、この地域に眠る文化の価値をさらに高めようと、その特徴である細ちぢれ麺の製造に注力します。私たちの想いは、やがて地域の製麺所や飲食店をも巻き込む力となり、今日の「高山ラーメン」というブランドを確立するに至りました。
2013年頃からは、ラーメン製造に特化し、スーパーや小売店向けの商品を展開しています。さらに2020年には高山市の老舗ラーメン店「豆天狗」を事業承継し、飲食業への進出も果たしました。
そして、近年では、独自開発した「生麺長期保存技術」を足掛かりに、海外への本格的な輸出やECサイトの強化といった多角的な販路開拓を推進しています。時代の需要に応えながら、一人でも多くのお客様へ私たちの麺を届けたいと考えています。
おかげさまで袋麺事業は好調に推移し、会社全体の直近の売上高は4億2,380千円となりました。2025年度には売上5億円を目指しています。
売上の80%は卸売が占めており、そのうちの70%以上が飛騨地方と、地域に深く根ざした事業を展開しています。
家業を身近に感じて育ち、入社するまで
私の実家は弊社の工場の隣にあったため、会社を家のように感じながら育ちました。学校から帰ると、機械で製麺する様子を眺め、簡単な手伝いをして過ごしていたことを覚えています。また、いつも夜遅くまで働く父の姿を見るうちに、子どもながらにも「いつか兄か自分のどちらかが、この会社を継ぐのだろう」と考えるようになりました。
地元の高校を卒業後は、進学のために上京し、亜細亜大学に入学しました。大学時代は、学業の傍らバックパッカーとして世界20カ国以上を旅して回りました。その中で得た多様な文化や人々との出会いが、私の視野を大きく広げてくれました。そして、「自分も何かを成し遂げたい」「世界を舞台にビジネスをしたい」という、これまでになかった強い意欲が湧き上がってきたのです。ただ、それは家業を継ぐことなのか、あるいは自分で起業することなのかは漠然としていました。
しかし、帰国後に改めて家業を見つめ直したとき、ゼロから新しいものを生み出すことだけが挑戦ではないと考えました。「歴史あるこの会社を次のステージへ導くことこそ、やりがいのある挑戦ではないか」と思い至り、大学卒業後の2013年、弊社に入社しました。
全方位で改革を続け、挑戦が文化になる
入社後は、まず製造ラインで業務を一通り覚えたのち、営業も担当するようになりました。
当時、会社はちょうどラーメン製造に一本化した頃でしたが、実は債務超過という深刻な財務状況でもありました。売上高も現在の4分の1程度の約1億2千万円で、再生フェーズの真っ只中でした。経営に関しては全くの素人だった私ですが「なんとかしなければ」と、とにかく行動することから始めました。
まず「プライドを全部捨てる」と決め、以前から経営の支援をしていただいていたMMPCコンサルティンググループの先生や、地元の先輩経営者の方々に頭を下げて実践を学び、同時に、経営書を読み漁っては必死に理論を吸収しました。
そして、会社の根幹に関わる改革として、財務体制の見直し、営業活動、製造工程の効率化を行いながら、ワークフローの整理やマニュアル整備といった地道な内部改善にも一つひとつ取り組みました。自らの手で形にしていくしかなかったため、とても苦しい時期でした。
しかし、学んで実践すればするほど改善点が見つかり、すぐに成果が表れていくことに気がつき、大きなやりがいと面白さを感じるようになりました。
入社から3年もすると、一つひとつの取り組みが実を結び、会社の数字は確かな手応えとして表れ始めました。何より嬉しかったのは、社員の顔つきが日に日に明るくなっていくのが分かったことです。社内の雰囲気も好転し、売上が右肩上がりに伸びていく実感を社員全員と共有できたのは、何ものにも代えがたい貴重な経験でした。
そして、会社が軌道に乗り始めた2017年、父からの「会社を任せたい」という事業承継の打診を受けて、28歳で代表取締役社長に就任しました。
老舗ラーメン店「豆天狗」のM&A、「製販一体」のビジネスモデルへ
学生時代、ラーメン店巡りが趣味だった私には、「いつか自分の店を」という夢がありました。その想いを胸にしていた2020年、長年の大切な取引先であった地元の老舗ラーメン店「豆天狗」から「後継者がいない、引き継いでくれないか」という相談がありました。
もし引き継がずに豆天狗のブランドがなくなれば、コラボレーション商品などの関連商品の売上が失われるという経営上の懸念がありました。と同時に、もし事業を引き継いだら製麺所として自社の麺の価値を直接お客様に届けられる絶好の機会でもあると考えました。そして、「私たちの手でこのブランドを守り、育てよう」と事業承継を決意しました。
もともと豆天狗は家族経営でしたが、事業承継を機に退かれ、弊社の社員が運営を引き継ぐことになりました。弊社としては初めての飲食店経営でしたが、ブランドの味を守り、新しい挑戦に踏み出す社員を支える責任は、全て私にあると覚悟を決めました。
まずは私自らが先頭に立ち、社員たちとゼロから店づくりを始めました。
製麺事業の再生フェーズで培った、製造工程の標準化やマニュアル化といったノウハウを店舗運営にも応用し、味の再現やオペレーションなどスムーズに軌道にのせることができました。今ではインバウンドのお客様にも愛される人気店として、安定的に成長しています。
豆天狗の事業承継により弊社のビジネスモデルは「製販一体」へと昇華させることが出来ました。消費者の声を聞くことのできる機会が持てたことで、全ての社員がさらに「お客様の為に」という気持ちで物事を判断するようになりました。
変化を恐れない企業文化
私が社長に就任してからは、「飛騨で誇れる会社創り」という経営理念を新たに掲げました。 これは、単に製品の質が良いということだけでなく、働きやすさや企業としての品位、地域貢献といったあらゆる側面で、地域の人々に「この会社があってよかった」と誇りに思っていただけるような企業を目指す、という決意を込めています。そして何より、社員一人ひとりが「自分たちの会社は素晴らしい」と自信を持てる、そんな企業像を追求するものです。
この理念を浸透させるために、毎月の会議で必ず理念に立ち返る時間を作っています。会社が目指す方向性を繰り返し確認することで、社員全員が同じ想いを共有できるよう努めています。この理念の根底には、弊社に深く根付いている「変化を恐れない」という企業文化があります。
以前から在籍している社員は、会社が債務超過のどん底状態から再生していく過程を、身をもって知っていることもあり、「変わっていかなければ会社は成長できない」という共通認識が、新しく入った社員にも自然と浸透しています。
また、チームとしては、それぞれが得意分野で力を発揮する体制ができています。例えば、私の兄は経営の最前線に立つのではなく、総務や製造現場を支える「縁の下の力持ち」の役割を担ってくれています。このように、一人ひとりがそれぞれの力を発揮し、互いを補い合う文化が、会社全体の成長を支える大きな力になっています。
社員に任せる姿勢が未来を創造する
弊社の社員は20名ほどで、一人ひとりの顔が見える距離の近さが、強い信頼関係を育んでいます。社風も、「風通しが良く、オープンで協調的」と感じます。私自身、社長という立場に固執せず、社員との積極的な交流を大切にしています。例えば、自分から飲み会に参加して仕事以外の話をしたり、日頃から雑談を交わしたりと、できるだけフラットな関係性を築くことを心がけています。
素直で真面目な社員が多く、私の意見や会社の新しい方針を前向きに受け止め、実直に実行に移してくれます。特に、私より年上の中途採用の社員たちは経験豊富でありながらとても意欲的で、「若い社長に負けていられないな」と笑顔で話してくれる姿には、私が逆に大きな刺激とエネルギーをもらっています。
社員の教育・育成において、心がけているのは「権限移譲」です。新しい取り組みを始める際は、まず私が責任者としてある程度まで道筋をつけて形を作りますが、プロジェクトが軌道に乗ったと判断したら、すぐに担当者に権限を移譲し、完全に任せます。
日々の業務におけるほとんどの決定は社員に委ねており、私が最終判断を下すのは全体の1割程度に過ぎません。社員の当事者意識の向上に繋がり、自己成長意欲の高い組織になっています。
「生麺×長期保存」のブルーオーシャン市場で海外へ
現在、私たちが最も力を入れているのが海外展開です。麺類を輸出する場合、保存性の理由から乾麺が主流です。しかし、弊社の40年以上研究してきた技術力を活かせば「生麺」を提供できるのではないかと思いました。商品開発には時間もコストもかかりましたが、どうしても本来の日本ラーメンの美味しさを海外の方に届けたいと一切の妥協を許すことなく作り続けました。
高山ラーメンに最適なタンパク質量の多い特注小麦粉で「細さ・伸びにくさ・うまさ」の黄金比、さらにセラミック等で濾過した水を練りこむ等の独自の技術により、風味を一切損なうことなく生麺を常温で長期間保存できる、独自の「生麺長期保存技術」を確立することが出来ました。
約8年もの試行錯誤を経て完成したこのノウハウは、他社には決して真似のできない、私たちの誇りです。結果として、私たちは「生麺×長期保存」というブルーオーシャン市場を切り拓くことができたと自負しています。このこだわりと技術は、HACCP認定やSDGs宣言といった、社会的な信頼性によっても裏付けられています。
この「生麺×長期保存」を武器に本格的な海外展開へと進めています。現在は台湾、シンガポール、カナダなどへ展開し、まだ年商1,000万円規模ですが、将来の大きな柱として育てています。
地域に根ざしながら歩みを進める
創業80周年を見据え、私たちはこれからも「飛騨だからできる」ことを証明していきます。私たちは飛騨という小さな町から、挑戦し、成果を上げ、その価値を発信し続けていきます。
そのためにも、私たちが果たすべき役割は2つあると考えています。
一つは、地域資源「飛騨高山ラーメン」の魅力を国内外へ発信し、その文化を守り継ぐことです。
そしてもう一つは、過疎化が進むこの地だからこそ事業を成長させ、雇用の創出や地元とのコラボレーションといった形で地域に貢献し、ここに暮らす人々の誇りを育んでいくことです。
この使命を果たすため、私たちは「海外事業」と「ラーメン店事業」を両輪で力強く推進しています。海外事業では、「生麺で世界を席巻する」という大きな夢を、必ず達成すべき未来像として捉えています。現在は売上全体の約0.3%と黎明期ですが、アジアに加え、カナダやアメリカ、ヨーロッパへの展開も進め、数年内に会社全体で売上7億円規模への成長を見込んでいます。
一方、ラーメン店事業では、来る2025年8月に高山市に新店舗をオープンし、3店舗体制とします。最新の省力化設備を導入するこの新店舗をモデルケースとして、今後の多店舗展開やフランチャイズ化も見据えた運営体制を構築し、2030年には、ラーメン部門全体で年間売上1億5,000万円超を目指しています。
どんなに老舗企業になっても、気持ちは挑戦者です。常に「飛騨であることの誇り」を胸に、変革を創造し、飛騨の未来発展に貢献していきます。
会社概要
| 社名 | 有限会社麺の清水屋 |
| 創立年 | 1948年 |
| 代表者名 | 代表取締役 清水 將行 |
| 資本金 | 300万円 |
| URL |
https://www.hidamen.net/
|
| 本社住所 |
〒506-1121 |
| 事業内容 | ・めん類製造業(生中華めんの製造・販売) ・飲食業 |
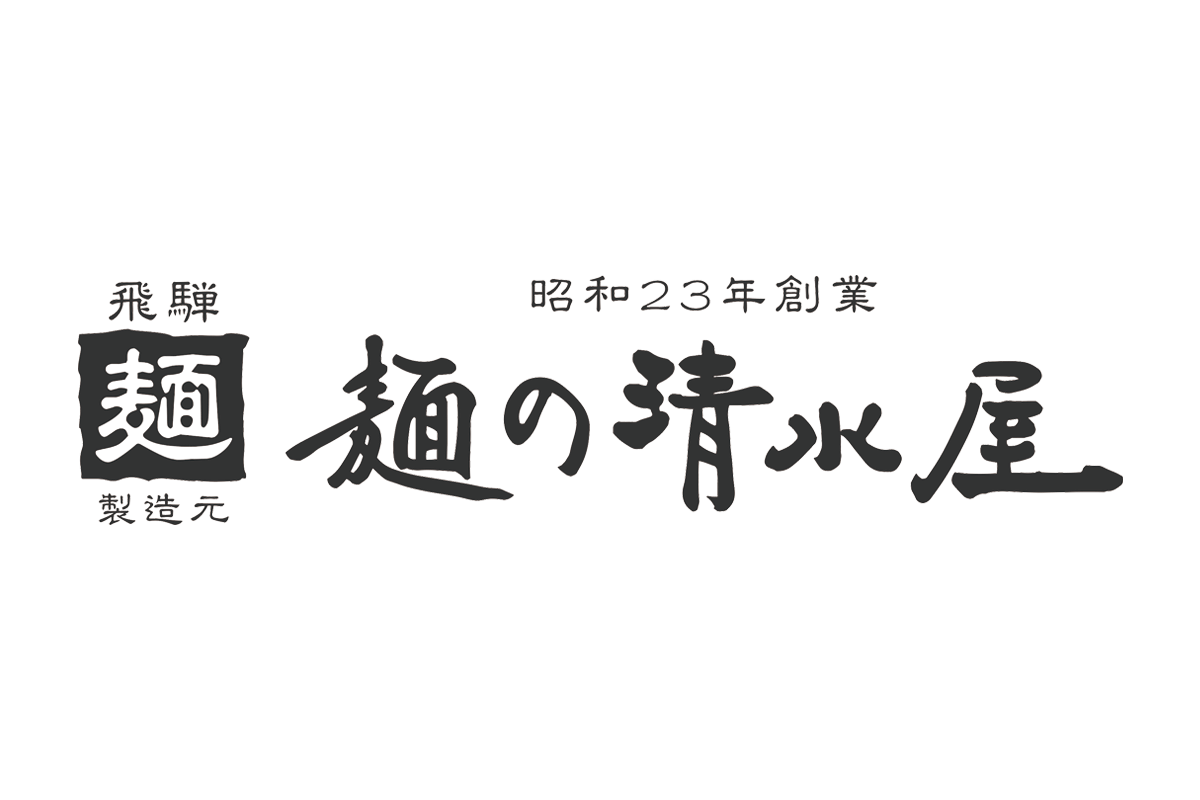

会社沿革
| 1948年 | 創業 |
| 2020年 | ラーメン店『豆天狗』をM&A |
有限会社麺の清水屋の経営資源引継ぎ募集情報
人的資本引継ぎ
岐阜県
世界を目指す製麺会社が人財を希望
事業引継ぎ
富山県
石川県
福井県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
世界を目指す製麺会社が事業引継ぎを希望
公開日:2025/07/25
※本記事の内容および所属名称は2025年7月現在のものです。現在の情報とは異なる場合があります。
この企業を見た方はこれらのツグナラ企業も見ています
ツグナラ企業へのお問い合わせ
本フォームからのお問い合わせ内容はツグナラ運営事務局でお預かりし、有意義と判断した問い合わせのみツグナラ企業にお渡ししています。営業目的の問い合わせ、同一送信者による大量送付はお控えください。



