
大阪・大阪市東淀川区
大阪 ・ 大阪市
東京 ・ 千代田区
愛知 ・ 名古屋市

引継ぎ実績あり
モータの製造販売と
株式会社FEW
相互発展と価値創出の可能性を秘めた老舗企業の「1個づくり品質」
経営理念
「利他共栄の経営と人づくり」
あなたは「自分のことしか考えない」利己のひとですか?「相手によかれ」と思える利他のひとですか?
利己の人は視野が狭くなり、人生を生きるうえで多くのものを失い益々卑屈になります。利他の心をもち相手を思いやることで、広い視野をもち深い友情に恵まれます。相手の気持ちを理解することも重要です。多様化が進んだ今、人それぞれの経験や境遇があります。理解できないと決めつけるのではなく、少し踏み込んで話をしてみましょう。そしてもう一つ、利他というのは相手に甘すぎでもいけません。相手のことを思うのであれば、時には厳しく突き放すことも必要です。大事なのは相手の気持ちを理解しようとすることです。
代表者メッセージ
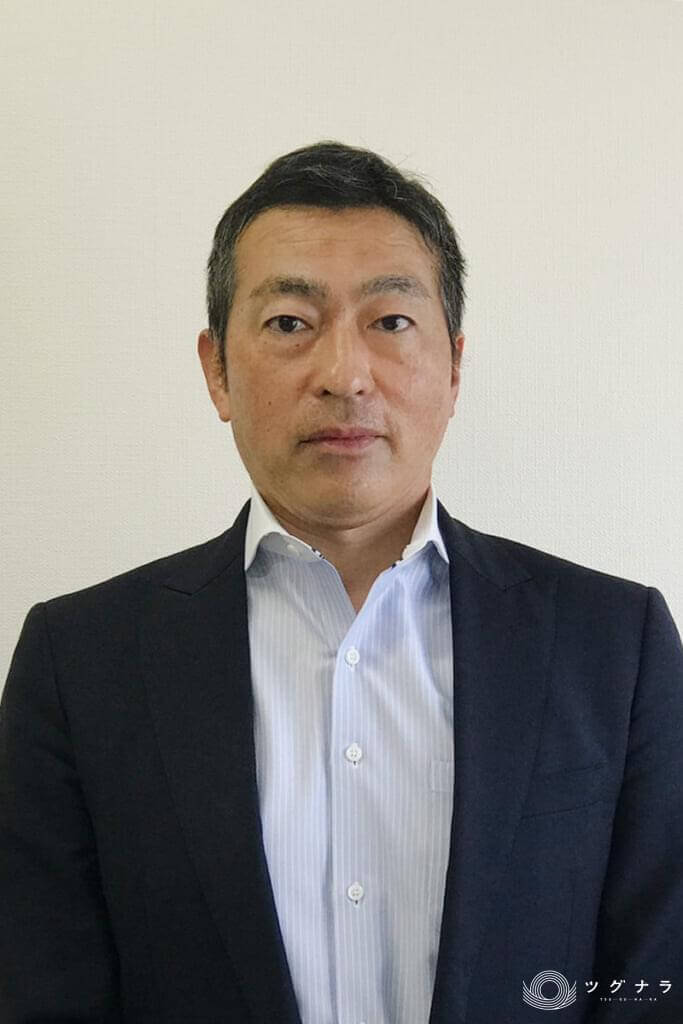
私どもは、1920年の創業以来、モータ製造一筋で100年を迎えることができました。
これもひとえに、お取引先様をはじめ弊社に関わる皆様方のご支援と、従業員の日々の努力の賜物と深く感謝しております。
モノを動かすには必ずモータが必要であり、モータはさまざまな設備や聞きの動力源、制御装置で社会基盤を支えてきました。
昨今は、IoTなどの分野で緻密な制御ができるモータも多数開発され、かつては想像できないような便利な世の中になってきています。一方で、モータそのものの特性を生かした製品も分野を問わず活躍しています。
私たちは、長年にわたり培われた実績を糧に、オンリーワンの企業を目指します。お客様が私どもに求めるものは千差万別で、品質や納期はもちろんですが、「他に作っている会社がないのでとにかく作り続けてほしい」や原子力や宇宙、深海向けなど特殊な用途向けにカスタマイズが必要なケースもあります。この為規模だけを追わず「お役に立てる」ことを大事にして参りたいと考えております。
日本では、少子高齢化や急激に進むグローバル化の影響もあり、年間3万社を超える製造会社が廃業に追い込まれています。厳しい環境下ではありますが、自社の特徴を活かし協力企業と力を合わせ、日本のものづくりを後世に引き継いでいきます。
まだまだ不十分な点ばかりですが、多くの方のお役に立てることができるように日々努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
代表取締役 仲下 正一
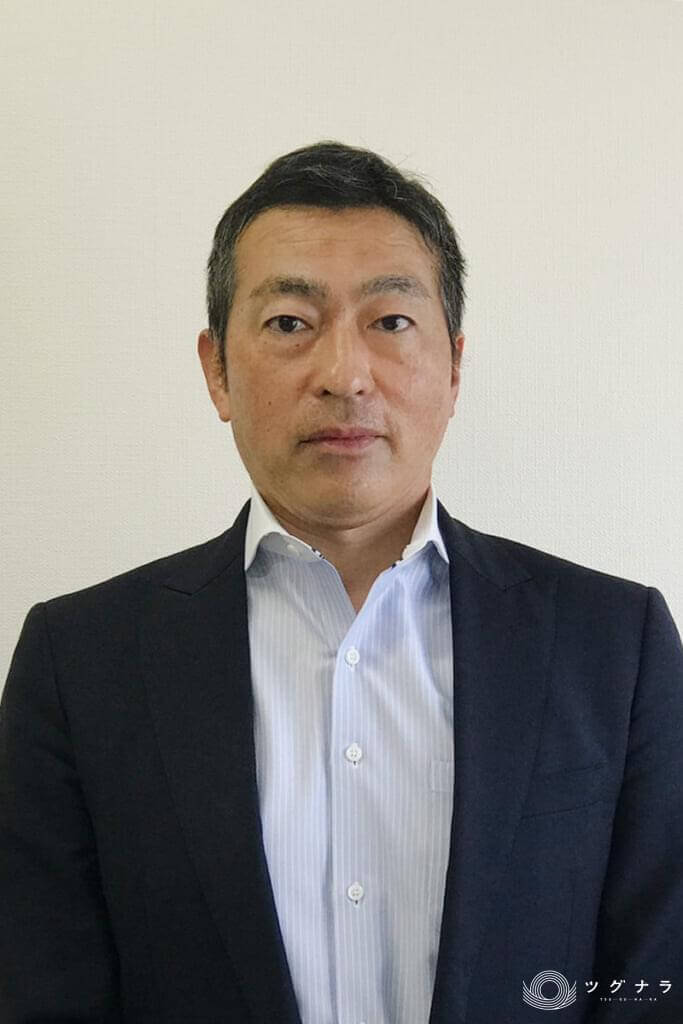
私たちのこだわり
個人事業から大手電動機メーカーの協力工場へ
モーターの製造販売を行う弊社は、1921年に創業者である藤井が個人事業として始めました。1953年に法人化し、その後、電機製品の製造販売を行っていた安川電機製作所(現株式会社安川電機)とのご縁により出資を受けました。1985年には、和歌山県に生産子会社である日本エレクトリックを設立し、長年にわたり安川電機からの仕事を請け負ってきたそうです。先々代までは安川電機を卒業された方が役員として弊社に入り、代表を務めていました。
2014年から2015年にかけては、東京証券取引所でコーポレートガバナンス・コードが導入されたことで内部統治の強化が求められるようになり、安川電機の傘下にあった弊社は、出資率100%の子会社化か、資本関係を断つかの選択を迫られました。当時代表だった私の前任は、安川電機から全ての株式を買い戻し、資本関係こそなくなりましたが、現在も外部の協力工場という位置づけとなっています。
銀行員のバイタリティの高さに感化され三和銀行に入行
私は、兵庫県出身です。母は薬剤師として自宅で薬店を営んでいました。商品棚には、薬だけではなく化粧品やパンなど様々な商品が置かれ、いつも地元のお客様で賑わっていたことを覚えています。
小学校から高校までほとんどの学年で学級委員長を務め、クラブ活動は水泳部を中心に取り組んできました。今振り返ると「困っている人の役に立ちたい」という想いは、この頃からあったのかもしれません。大学受験の時には、親に金銭的な負担がかからないように、そして他の大学に通う姉と下宿生活ができるようにと神戸の兵庫県立神戸商科大学に進学しました。ここでも体育会水泳部に入り、幹部時代は副主将とOBとの窓口となる役職を兼務し、厳しい練習と組織運営を通して人との付き合いを学びました。
1990年の就職活動時は、バブル期の急激な経済成長で民間企業は人手不足となっており、バブル崩壊の兆しはあったものの、学生の獲得を巡り企業が激しい採用活動をしていました。私の元へも、都市銀行や大手保険会社、大手電機メーカーなどに就職した大学の先輩から、勧誘の電話が毎日4~6件かかってきておりました。複数の企業から内定をいただきましたが、その中でも銀行員の方のバイタリティの高さや懸命に頑張る姿に感化され、当時大阪府中央区に本店があった三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入行を決めました。
人や企業の役に立つやりがい、関係性の大切さを実感
三和銀行では初め明石支店に配属になりました。配属され半年がたった時期から担当を持たせてもらい中小企業の社長相手に叱られながらも、お客様のために走り回っていました。入行から3年目には塚本支店に配属となりました。塚本支店は大阪市淀川区にある小さな支店で、下町特有の雰囲気があり、お客様も全て中小企業や個人事業主でした。ここでは入行3年目とはいえ全ての業務を任されるようになり、業績推進や与信判断、融資、決算、本部への諸報告などの業務のほか、景気悪化による回収業務や複雑な相続関係の案件も増え、そのほとんどを一人で対応する日々でした。上司からも毎日のように叱咤され、非常に辛く苦しい時期ではありましたが、この経験により、働く意義を問い直すとともに仕事の知識も増え少し自信が出てきたような気がします。その後大阪市中央区の瓦町支店を経て、大手法人担当などを経験させてもらいました。また仕事以外では銀行水泳部のキャプテンを長年務め、銀行に在籍した15年間実業団の大会にも出場しました。
銀行勤務歴15年のうち後半の5年間は、難波支店、梅田支店、新設された新規開拓部門などに配属され、新規営業の先端部隊として活動に注力しました。銀行は何か商品を持っているわけではなく、形のないサービスをお客様に提供しています。このため、新規で取引を獲得するということは、商品で差別化するわけにいきません。担当者である自分自身がお客様に信頼してもらえる関係性づくりと、お客様の心に響く提案が最も大事だと実感しました。これを実際に行動に表すためには、お客様の抱える課題を自分なりに考えて、それを解決するような提案をし続けることが重要で、視野の広さやお客様の事業をしっかりと理解するということが大切な要素だと気付かされました。
お客様の心をつかむために、先方の課題をヒアリングして、銀行の膨大な取引先をデータベースをもとに検索し、先方に紹介する「お取引先紹介」という方法を多く使いました。銀行そのものはお客様の課題解決につながる技術やノウハウは持ち合わせてはいないですが、ご縁を繋ぐことで経営の役に立てることがあり、結果的に多くの新規取引先を獲得することができました。私自身も人のお役に立つということに誇りとやりがいを感じていました。
ただ、こういった地道な営業活動によりお客様と打ち解け、取引が開始されても、私から担当が変わると取引がなくなってしまうこともあり、むなしさを感じることも多々ありました。この為会社や組織という枠から一度出て、一人ひとりのお客様と長くお付き合いを続けていきたいという思いが生まれ、独立を考えるようになりました。
役員として内部統制の強化を図るとともに個人コンサル業を兼務
銀行退職後は、一層多くの気づきがありました。まずは収入を得るため生命保険会社に入社しましたが、人や企業の役に立つ仕事をしたいという思いは変わらず、2007年には会社を設立し、保険代理店を営みながら個人でコンサルティング業をスタートしました。
コンサルタントとしてお客様に向き合い経営者の悩みや課題を聞くうちに、会社のパフォーマンス向上のためには組織構築、社員教育など内部の活性化が必要だと考えるようになり、社員のミーティングや役員会に入り、相手先と同じ目線に立ちアドバイス等を行いました。
2008年には、ある方の紹介で外部の専門家として、兵庫県にある神津製作所(現TMT神津)の経営支援を行うこととなりました。神津製作所は、2000年に経営難により民事再生を申し立て、自己再建中でした。2005年頃には徐々に自己再建が進み、炭素繊維という特殊素材向けワインダーを世界で唯一扱っていたこともあって、V字回復を遂げていました。ところが、私が外部で経営参画をし、株周りを調べていくうちに株式が298人に分散していることがわかりました。更には株主単位での相続手続きもなされてないため、連絡がつかない株主も多く存在しました。非上場株式が分散した場合、会社としての意思決定が困難になるリスクがあり、承継どころか存続も危うい状態でした。当初は他社と同様に外部コンサルタントとして援助をしていくつもりでしたが、当時の経営者からも要請があったので、神津製作所の役員に就任させていただき、資本政策を本格的に行うことにしました。
具体的には分散している株を集約するため、株の保有者に直接電話や訪問をし、半数以上の株式を時間をかけて買い集め、当時の経営陣に集約し、その後事業承継ファンドに手伝っていただき株を移転することで資金的な問題も同時に解決しながら、経営が安定する水準まで集約を進めることができました。その後は同社の取締役として経営全体を担うつもりで同社の仕事に比重を移していきました。
生き残りをかけ資本提携とリストラに踏み切る
神津製作所に外部専門家として入った2008頃には、リーマンショックによって世界景気がガタガタになりました。同社の売上もピークから3分の1まで落ち込み、リーマンショック前に炭素繊維メーカーが大幅な設備投資を行っていたこともあって、業界の設備過剰状態が続き、同社の業績は長く低迷しました。資本政策は進めることができましたが、肝心かなめの本業の回復が一向にうまくいかないのです。また機械メーカーとしては絶対に必要な新規開発も人材難で進みません。こういった環境下で、生き残りをかけて、2012年繊維機械の大手メーカーであるTMTマシナリー株式会社と資本業務提携を締結しました。当時は、繊維機械メーカーは全世界的に過当競争(同業種による過度の競争状態)が激化し、業界では合従連衡(状況や利害に応じて組織、企業が結びついたり離れたりすること)が進んでいました。スイスやアメリカの企業からも当時の社長宛に具体的に会社買収の話が来ていました。私は一取締役ではありましたが、当時の社長を初め、こういった事業の抜本的な変革には不慣れであったため、私が主になり資本業務提携をまとめました。
2012年時点では50%の株をもっていただき、T社の傘下として再スタートを切りましたが、本業での苦しい状況は続いており、2014年には身を切る思いで約20人の人員整理を行いました。この時も私自身が当事者となり進めましたが、精神的に一番辛い時期だったと思います。リストラを機に前社長に退任いただき、私自身も会社を去る決意をしていましたが、親会社からの慰留を受け、2015年から約5年間、TMT神津で代表をしました。このタイミングで親会社の資本も100%にして完全子会社に転換させました。
この12年間は非常に苦しい時期でしたが、外部のアドバイザーではなく、経営陣、代表者として中小企業でものづくりの現場に携われたことは貴重な経験だったと思います。従業員の方と膝を突き合わせて話込み、信頼関係を作るという毎日が自分には合っていると実感しました。ただ子会社の代表は重要な経営事項は決めることが出来ません。もう一度自分の力で経営に挑戦したいと思い、ご縁探しを始めました。
代表就任を機に、社内外の体制と信頼関係の再構築を決意
TMT神津の代表だった当時、仕入先をしっかり回ろうと考え、個々の外注先へ訪問したり、仕入先を集めて事業説明会を開催したりしました。その仕入先の中に、弊社がありました。こういった活動の中で弊社の前代表と話す機会があり、「世代交代を検討している」と聞いていました。結果的に事業を引き継ぐことで合意がとれ、2020年4月に弊社に入社しました。
ところが入社後、私の前任はそれまであっていた人物とは大きく違うことが分かりました。実際の経営は度を越えたワンマン経営で、実際は私に事業を引き継ぐ気がなく、複数の役職員が「後任といってひとを連れてくるが、定着したことがない」というなど、事業を引き継ぐという思いは到底叶わない状況であったのです。現実は自分の思いとはずいぶんと違っていたので、一旦会社を辞めて違う道に進むこともかんがえました。しかし当時の取締役3人とグループ会社の取締役3名から「今この会社は体制を変えないと未来がない」と口をそろえて強い慰留を受けました。会社の行き先を大きく変える決断の重さに悩みましたが、後継者候補として関わったからには、会社や社員を守り良い方向に導いていく責任があると考え、代表就任を決意しました。
結果的に、突然の代表交代となってしまいましたが、新代表として就任直後にお客様に事情説明に訪問した際には、非常に驚かれたものの受け入れていただけたこと、社内から退職者が出なかったことは大変ありがたいことでした。代表就任を機に、社内外の信頼関係や体制を一から作り直していこうと固く決意しました。
自分の考えを導き出し経営の視野を養う「経営塾」
現在は正社員約60人、パート約20人です。生産子会社である和歌山県の日本エレクトリック(資本関係では親会社になりますが)の社員20~30人も含めると、約100人が働いています。
入社から約3年が経った2023年2月には、理念を「利他共栄の経営と人づくり」に刷新し、それまで続けてきた改革を次のステップに進めるべく動き出しています。幹部人材も2021年度には技術部長、2022年度には製造部長と経験豊富な人材の補強が進みフォーメーションがだいぶ固まってきています。
新製造部長は過去に中小企業で経営塾に携わってきた経験があったため、弊社でも幹部候補のための「経営塾」を始めました。現在は20代から50代の選抜者6人が月2回、終業後に集まり、経営者として必要な考え方を学びの中から探し出す取り組みを行っています。リーダーシップを発揮していくには、まず自分の意見をもつことが大事になります。人に喜ばれる経営や、信頼されるためには自分は何を考え、どう行動するべきなのか?といった問いの中から自分の考えを導き出し、同じ幹部候補同士で議論し合えるようになれば、自ずと経営者に近い目線で物事を見ることができるようになるのではないかと思っています。選抜者は年齢も職種も就業年数も様々ですが、気後れせずまず自身が成長し、会社の成長と変化を楽しんでもらえたらと思っています。
全社員が視野を広げ活躍できる環境へ
また、幹部候補だけでなく、全社員が人の役に立ち、感謝される経験をしてもらいたいと思っています。人生は、人との出会いにより築かれていくもので、出会いによって随分と変わるものだと思います。志や意識が高い人と同じ時間を過ごすことで自信の意識も高まるものです。こういったきっかけ一つで人生は大きく変わっていきます。自身が人の役に立ちたいと本気で考え、そのために成長しようと努力していれば、自然と目線の高い人と付き合うようになり、その交流の中でさらに上へと引き上げられることもあります。会社に在籍する人たちが、互いを高め合える環境づくりをしてそれにより更に周りの人たちが良い影響を受けるといったことで人として成長してほしいと思っています。
組織の基盤は徐々に整いつつあり、次のステップとしては、2023年9月に社名変更を行う予定です。社名変更には、会社を未来に向けリスタートさせこれからの社会でも存在価値を認めてもらえる会社になろうという決意を込めています。自分たちの仕事に誇りをもち相手を思いやることができる人財を作り、社員が様々な分野で活躍できる会社になっていけたらと思っています。
設備投資コストを抑え継続生産をサポートするEOL復活
モーターは成熟技術であり他社との差別化がしにくいため、いかにコストを抑えるものづくりをするかが重要なポイントになります。大手メーカーは、自動化などで徹底的に内製化をすすめ生産コストを極限まで抑える活動をされています。そのため一定の量が販売できなくなると、コストが合わなくなります。結果的に該当の型式の生産を中止することになり、弊社ではそういった大手メーカーのレガシー製品(新規格・製品の発売などにより型落ちとなった製品)の代替品の製造を求められるケースが多くあります。特に安川電機様とは長年協力工場の位置づけで、レガシー製品の生産を継続しています。また手作業の多い型式のOEMも行っています。
EOL(製造中止品)復活の個別対応ができる工場は少ないので、弊社をよりどころとしているお客様先も多く「作ってもらえるだけでありがたい」といった感謝の言葉も多くいただきますが、その気持ちにあぐらをかいていてはこの先事業は続かないだろうと思っています。相談内容や予算にもよりますが、他社が対応できないような細かい要望にもできる限り対応していくことで、困っている企業の役に立ち、信頼される関係性を大事にしていきたいと考えています。
モーター分野での付加価値を高める「1個づくり品質」
ただ過去から長年にわたり、お客様からのご要求に応える活動のみをしてきたため、自分たちのものづくりに対する考えやこだわり、ルールがかなり不足しています。お客様の要求を聞き応えると言えば、聞こえはいいですが、結局「等身大」のものしかできません。結果的に部品の点数が膨大になり、在庫部品も増え続けます。コストの低減も限界があり今後のことを考えると、今のやり方では限界が来るのは明らかです。この為、2022年度から「1個作り品質」という言葉を使い、根本的に仕事の考え方やり方を変えていく取組を始めています。これを完遂するには、営業はお客さま単位で将来の販売予想などを掴まないといけませんし、技術は設計ポリシーをもって、標準化、共通化をおこなっていかないといけません。調達部門も必要な個数だけ買って余計な在庫を作らないという骨太な思想がないとできません。簡単なことではありませんが、なおさら弊社の存在価値の一つになると考えており、一つ一つ難題に向き合っていきたいと考えています。
また今後はモーターのコア技術向上とともに事業の付加価値を追求し、アクチュエーター(モーターの回転を任意の運動に変換し駆動させる装置)や制御装置を組み合わせたモジュール製品分野にも参入していきたいと考えています。
M&Aの一歩手前、組合方式での協業促進システムを考案
中小企業は人財や資金などのリソースが限られ、できることが限定されます。一方で外部環境は刻刻と変化しその変化のスピードが激的に速くなっています。この為経営者の方々もどうしていいのかわからない、課題はわかっているが手をつけられないといったスパイラルに陥っています。以前は大手企業の下請けをしていると、品質などの教育もしてもらえ、必死についていくことで売上や利益が捻出されていました。しかし今は大手メーカーにもかつての力はなく、逆に値上げ要求を聞いてもらえないなど、経営の頭痛の種にさえなりかねません。外部環境の変化に順応することが非常に重要ですが、それが出来ずに時間だけが経過している状況を根本的にかえていくことが必要なのではないかと考えるようになりました。
これに対しては、中小企業同士がもっと協力しあえる枠組みや行動が一つの策と考え、我々も独自でデータベースを基に様々な企業に直接手紙を書いて提案を始めています。思った以上に話を聞いてみたいという反応も多く、直接お伺いしたりWEBで面談をさせていただいたりしています。そこで中小企業の悩みはやはり共通する部分があるということに改めて気づかされました。今、事業承継、M&Aといった話は頻繁にされており、それを仲介する会社も日に日に増えている感があります。しかし、事業承継というのは後継者がいればできるといった単純な話ではありません。まるでものを売るように扱っている会社もあることに違和感を覚えています。まずは互いの信頼関係をつくり考え方の腹落ちをする時間も必要です。
ならば自分たちで課題を解決できるようにしていこうと考え、M&Aの一歩手前の解決策として、組合方式での協業促進システムをつくろうと考えました。手紙をおくることで新たに知り合った会社経営者に、じっくりと話をする時間をつくっていただき、徐々にこういった枠組みの話を進めています。
他社の経営者と一緒に困っている部分を重点的に解決し相互補完できる、ちょうどいいコスト感のシステムであれば、他社との協業も促進され、互いに企業価値を上げていくことができれば、ステークホルダーにとっても大きなメリットとなるはずです。
中小企業全体の底上げと活性化を可能するソリューション
協業によって他社との交流が生まれれば、社員の活性化も図れるのではないかと考えています。私も銀行で優秀な人たちと切磋琢磨してきた経験がありますが、中小企業はそういった機会もすくなく、自分の現在地を客観的にみるということはできません。競争や刺激を得る機会づくりも人を成長させる重要なことだと思います。中小企業にエネルギーがないのは人の成長が簡単に実現できないことも大きな要因だと思います。ものづくりを通じていろいろな企業と交流が促進されれば、社員の活躍の場、成長の場が広がることにもなると考えています。
今後は各社の課題をメニュー化して、組合価格で提供できるようなシステムを構築したいと思っています。弊社の事業領域を広げることにもつながりますし、より多くの方に協業のメリットを伝え、実際にソリューションを体験してもらいながら地域企業の意識を変え、中小企業全体の底上げをしたいという強い想いが根底にあります。企業や地域で働く多くの人たちが自分自身でしっかりと考え行動に移す意欲を喚起していかなければ、日本が抱える根本的な問題は解決しません。成長に踏み出す一歩として勇気を持ってもらえたらと思っています。
個人事業から大手電動機メーカーの協力工場へ
モーターの製造販売を行う弊社は、1921年に創業者である藤井が個人事業として始めました。1953年に法人化し、その後、電機製品の製造販売を行っていた安川電機製作所(現株式会社安川電機)とのご縁により出資を受けました。1985年には、和歌山県に生産子会社である日本エレクトリックを設立し、長年にわたり安川電機からの仕事を請け負ってきたそうです。先々代までは安川電機を卒業された方が役員として弊社に入り、代表を務めていました。
2014年から2015年にかけては、東京証券取引所でコーポレートガバナンス・コードが導入されたことで内部統治の強化が求められるようになり、安川電機の傘下にあった弊社は、出資率100%の子会社化か、資本関係を断つかの選択を迫られました。当時代表だった私の前任は、安川電機から全ての株式を買い戻し、資本関係こそなくなりましたが、現在も外部の協力工場という位置づけとなっています。
銀行員のバイタリティの高さに感化され三和銀行に入行
私は、兵庫県出身です。母は薬剤師として自宅で薬店を営んでいました。商品棚には、薬だけではなく化粧品やパンなど様々な商品が置かれ、いつも地元のお客様で賑わっていたことを覚えています。
小学校から高校までほとんどの学年で学級委員長を務め、クラブ活動は水泳部を中心に取り組んできました。今振り返ると「困っている人の役に立ちたい」という想いは、この頃からあったのかもしれません。大学受験の時には、親に金銭的な負担がかからないように、そして他の大学に通う姉と下宿生活ができるようにと神戸の兵庫県立神戸商科大学に進学しました。ここでも体育会水泳部に入り、幹部時代は副主将とOBとの窓口となる役職を兼務し、厳しい練習と組織運営を通して人との付き合いを学びました。
1990年の就職活動時は、バブル期の急激な経済成長で民間企業は人手不足となっており、バブル崩壊の兆しはあったものの、学生の獲得を巡り企業が激しい採用活動をしていました。私の元へも、都市銀行や大手保険会社、大手電機メーカーなどに就職した大学の先輩から、勧誘の電話が毎日4~6件かかってきておりました。複数の企業から内定をいただきましたが、その中でも銀行員の方のバイタリティの高さや懸命に頑張る姿に感化され、当時大阪府中央区に本店があった三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入行を決めました。
人や企業の役に立つやりがい、関係性の大切さを実感
三和銀行では初め明石支店に配属になりました。配属され半年がたった時期から担当を持たせてもらい中小企業の社長相手に叱られながらも、お客様のために走り回っていました。入行から3年目には塚本支店に配属となりました。塚本支店は大阪市淀川区にある小さな支店で、下町特有の雰囲気があり、お客様も全て中小企業や個人事業主でした。ここでは入行3年目とはいえ全ての業務を任されるようになり、業績推進や与信判断、融資、決算、本部への諸報告などの業務のほか、景気悪化による回収業務や複雑な相続関係の案件も増え、そのほとんどを一人で対応する日々でした。上司からも毎日のように叱咤され、非常に辛く苦しい時期ではありましたが、この経験により、働く意義を問い直すとともに仕事の知識も増え少し自信が出てきたような気がします。その後大阪市中央区の瓦町支店を経て、大手法人担当などを経験させてもらいました。また仕事以外では銀行水泳部のキャプテンを長年務め、銀行に在籍した15年間実業団の大会にも出場しました。
銀行勤務歴15年のうち後半の5年間は、難波支店、梅田支店、新設された新規開拓部門などに配属され、新規営業の先端部隊として活動に注力しました。銀行は何か商品を持っているわけではなく、形のないサービスをお客様に提供しています。このため、新規で取引を獲得するということは、商品で差別化するわけにいきません。担当者である自分自身がお客様に信頼してもらえる関係性づくりと、お客様の心に響く提案が最も大事だと実感しました。これを実際に行動に表すためには、お客様の抱える課題を自分なりに考えて、それを解決するような提案をし続けることが重要で、視野の広さやお客様の事業をしっかりと理解するということが大切な要素だと気付かされました。
お客様の心をつかむために、先方の課題をヒアリングして、銀行の膨大な取引先をデータベースをもとに検索し、先方に紹介する「お取引先紹介」という方法を多く使いました。銀行そのものはお客様の課題解決につながる技術やノウハウは持ち合わせてはいないですが、ご縁を繋ぐことで経営の役に立てることがあり、結果的に多くの新規取引先を獲得することができました。私自身も人のお役に立つということに誇りとやりがいを感じていました。
ただ、こういった地道な営業活動によりお客様と打ち解け、取引が開始されても、私から担当が変わると取引がなくなってしまうこともあり、むなしさを感じることも多々ありました。この為会社や組織という枠から一度出て、一人ひとりのお客様と長くお付き合いを続けていきたいという思いが生まれ、独立を考えるようになりました。
役員として内部統制の強化を図るとともに個人コンサル業を兼務
銀行退職後は、一層多くの気づきがありました。まずは収入を得るため生命保険会社に入社しましたが、人や企業の役に立つ仕事をしたいという思いは変わらず、2007年には会社を設立し、保険代理店を営みながら個人でコンサルティング業をスタートしました。
コンサルタントとしてお客様に向き合い経営者の悩みや課題を聞くうちに、会社のパフォーマンス向上のためには組織構築、社員教育など内部の活性化が必要だと考えるようになり、社員のミーティングや役員会に入り、相手先と同じ目線に立ちアドバイス等を行いました。
2008年には、ある方の紹介で外部の専門家として、兵庫県にある神津製作所(現TMT神津)の経営支援を行うこととなりました。神津製作所は、2000年に経営難により民事再生を申し立て、自己再建中でした。2005年頃には徐々に自己再建が進み、炭素繊維という特殊素材向けワインダーを世界で唯一扱っていたこともあって、V字回復を遂げていました。ところが、私が外部で経営参画をし、株周りを調べていくうちに株式が298人に分散していることがわかりました。更には株主単位での相続手続きもなされてないため、連絡がつかない株主も多く存在しました。非上場株式が分散した場合、会社としての意思決定が困難になるリスクがあり、承継どころか存続も危うい状態でした。当初は他社と同様に外部コンサルタントとして援助をしていくつもりでしたが、当時の経営者からも要請があったので、神津製作所の役員に就任させていただき、資本政策を本格的に行うことにしました。
具体的には分散している株を集約するため、株の保有者に直接電話や訪問をし、半数以上の株式を時間をかけて買い集め、当時の経営陣に集約し、その後事業承継ファンドに手伝っていただき株を移転することで資金的な問題も同時に解決しながら、経営が安定する水準まで集約を進めることができました。その後は同社の取締役として経営全体を担うつもりで同社の仕事に比重を移していきました。
生き残りをかけ資本提携とリストラに踏み切る
神津製作所に外部専門家として入った2008頃には、リーマンショックによって世界景気がガタガタになりました。同社の売上もピークから3分の1まで落ち込み、リーマンショック前に炭素繊維メーカーが大幅な設備投資を行っていたこともあって、業界の設備過剰状態が続き、同社の業績は長く低迷しました。資本政策は進めることができましたが、肝心かなめの本業の回復が一向にうまくいかないのです。また機械メーカーとしては絶対に必要な新規開発も人材難で進みません。こういった環境下で、生き残りをかけて、2012年繊維機械の大手メーカーであるTMTマシナリー株式会社と資本業務提携を締結しました。当時は、繊維機械メーカーは全世界的に過当競争(同業種による過度の競争状態)が激化し、業界では合従連衡(状況や利害に応じて組織、企業が結びついたり離れたりすること)が進んでいました。スイスやアメリカの企業からも当時の社長宛に具体的に会社買収の話が来ていました。私は一取締役ではありましたが、当時の社長を初め、こういった事業の抜本的な変革には不慣れであったため、私が主になり資本業務提携をまとめました。
2012年時点では50%の株をもっていただき、T社の傘下として再スタートを切りましたが、本業での苦しい状況は続いており、2014年には身を切る思いで約20人の人員整理を行いました。この時も私自身が当事者となり進めましたが、精神的に一番辛い時期だったと思います。リストラを機に前社長に退任いただき、私自身も会社を去る決意をしていましたが、親会社からの慰留を受け、2015年から約5年間、TMT神津で代表をしました。このタイミングで親会社の資本も100%にして完全子会社に転換させました。
この12年間は非常に苦しい時期でしたが、外部のアドバイザーではなく、経営陣、代表者として中小企業でものづくりの現場に携われたことは貴重な経験だったと思います。従業員の方と膝を突き合わせて話込み、信頼関係を作るという毎日が自分には合っていると実感しました。ただ子会社の代表は重要な経営事項は決めることが出来ません。もう一度自分の力で経営に挑戦したいと思い、ご縁探しを始めました。
代表就任を機に、社内外の体制と信頼関係の再構築を決意
TMT神津の代表だった当時、仕入先をしっかり回ろうと考え、個々の外注先へ訪問したり、仕入先を集めて事業説明会を開催したりしました。その仕入先の中に、弊社がありました。こういった活動の中で弊社の前代表と話す機会があり、「世代交代を検討している」と聞いていました。結果的に事業を引き継ぐことで合意がとれ、2020年4月に弊社に入社しました。
ところが入社後、私の前任はそれまであっていた人物とは大きく違うことが分かりました。実際の経営は度を越えたワンマン経営で、実際は私に事業を引き継ぐ気がなく、複数の役職員が「後任といってひとを連れてくるが、定着したことがない」というなど、事業を引き継ぐという思いは到底叶わない状況であったのです。現実は自分の思いとはずいぶんと違っていたので、一旦会社を辞めて違う道に進むこともかんがえました。しかし当時の取締役3人とグループ会社の取締役3名から「今この会社は体制を変えないと未来がない」と口をそろえて強い慰留を受けました。会社の行き先を大きく変える決断の重さに悩みましたが、後継者候補として関わったからには、会社や社員を守り良い方向に導いていく責任があると考え、代表就任を決意しました。
結果的に、突然の代表交代となってしまいましたが、新代表として就任直後にお客様に事情説明に訪問した際には、非常に驚かれたものの受け入れていただけたこと、社内から退職者が出なかったことは大変ありがたいことでした。代表就任を機に、社内外の信頼関係や体制を一から作り直していこうと固く決意しました。
自分の考えを導き出し経営の視野を養う「経営塾」
現在は正社員約60人、パート約20人です。生産子会社である和歌山県の日本エレクトリック(資本関係では親会社になりますが)の社員20~30人も含めると、約100人が働いています。
入社から約3年が経った2023年2月には、理念を「利他共栄の経営と人づくり」に刷新し、それまで続けてきた改革を次のステップに進めるべく動き出しています。幹部人材も2021年度には技術部長、2022年度には製造部長と経験豊富な人材の補強が進みフォーメーションがだいぶ固まってきています。
新製造部長は過去に中小企業で経営塾に携わってきた経験があったため、弊社でも幹部候補のための「経営塾」を始めました。現在は20代から50代の選抜者6人が月2回、終業後に集まり、経営者として必要な考え方を学びの中から探し出す取り組みを行っています。リーダーシップを発揮していくには、まず自分の意見をもつことが大事になります。人に喜ばれる経営や、信頼されるためには自分は何を考え、どう行動するべきなのか?といった問いの中から自分の考えを導き出し、同じ幹部候補同士で議論し合えるようになれば、自ずと経営者に近い目線で物事を見ることができるようになるのではないかと思っています。選抜者は年齢も職種も就業年数も様々ですが、気後れせずまず自身が成長し、会社の成長と変化を楽しんでもらえたらと思っています。
全社員が視野を広げ活躍できる環境へ
また、幹部候補だけでなく、全社員が人の役に立ち、感謝される経験をしてもらいたいと思っています。人生は、人との出会いにより築かれていくもので、出会いによって随分と変わるものだと思います。志や意識が高い人と同じ時間を過ごすことで自信の意識も高まるものです。こういったきっかけ一つで人生は大きく変わっていきます。自身が人の役に立ちたいと本気で考え、そのために成長しようと努力していれば、自然と目線の高い人と付き合うようになり、その交流の中でさらに上へと引き上げられることもあります。会社に在籍する人たちが、互いを高め合える環境づくりをしてそれにより更に周りの人たちが良い影響を受けるといったことで人として成長してほしいと思っています。
組織の基盤は徐々に整いつつあり、次のステップとしては、2023年9月に社名変更を行う予定です。社名変更には、会社を未来に向けリスタートさせこれからの社会でも存在価値を認めてもらえる会社になろうという決意を込めています。自分たちの仕事に誇りをもち相手を思いやることができる人財を作り、社員が様々な分野で活躍できる会社になっていけたらと思っています。
設備投資コストを抑え継続生産をサポートするEOL復活
モーターは成熟技術であり他社との差別化がしにくいため、いかにコストを抑えるものづくりをするかが重要なポイントになります。大手メーカーは、自動化などで徹底的に内製化をすすめ生産コストを極限まで抑える活動をされています。そのため一定の量が販売できなくなると、コストが合わなくなります。結果的に該当の型式の生産を中止することになり、弊社ではそういった大手メーカーのレガシー製品(新規格・製品の発売などにより型落ちとなった製品)の代替品の製造を求められるケースが多くあります。特に安川電機様とは長年協力工場の位置づけで、レガシー製品の生産を継続しています。また手作業の多い型式のOEMも行っています。
EOL(製造中止品)復活の個別対応ができる工場は少ないので、弊社をよりどころとしているお客様先も多く「作ってもらえるだけでありがたい」といった感謝の言葉も多くいただきますが、その気持ちにあぐらをかいていてはこの先事業は続かないだろうと思っています。相談内容や予算にもよりますが、他社が対応できないような細かい要望にもできる限り対応していくことで、困っている企業の役に立ち、信頼される関係性を大事にしていきたいと考えています。
モーター分野での付加価値を高める「1個づくり品質」
ただ過去から長年にわたり、お客様からのご要求に応える活動のみをしてきたため、自分たちのものづくりに対する考えやこだわり、ルールがかなり不足しています。お客様の要求を聞き応えると言えば、聞こえはいいですが、結局「等身大」のものしかできません。結果的に部品の点数が膨大になり、在庫部品も増え続けます。コストの低減も限界があり今後のことを考えると、今のやり方では限界が来るのは明らかです。この為、2022年度から「1個作り品質」という言葉を使い、根本的に仕事の考え方やり方を変えていく取組を始めています。これを完遂するには、営業はお客さま単位で将来の販売予想などを掴まないといけませんし、技術は設計ポリシーをもって、標準化、共通化をおこなっていかないといけません。調達部門も必要な個数だけ買って余計な在庫を作らないという骨太な思想がないとできません。簡単なことではありませんが、なおさら弊社の存在価値の一つになると考えており、一つ一つ難題に向き合っていきたいと考えています。
また今後はモーターのコア技術向上とともに事業の付加価値を追求し、アクチュエーター(モーターの回転を任意の運動に変換し駆動させる装置)や制御装置を組み合わせたモジュール製品分野にも参入していきたいと考えています。
M&Aの一歩手前、組合方式での協業促進システムを考案
中小企業は人財や資金などのリソースが限られ、できることが限定されます。一方で外部環境は刻刻と変化しその変化のスピードが激的に速くなっています。この為経営者の方々もどうしていいのかわからない、課題はわかっているが手をつけられないといったスパイラルに陥っています。以前は大手企業の下請けをしていると、品質などの教育もしてもらえ、必死についていくことで売上や利益が捻出されていました。しかし今は大手メーカーにもかつての力はなく、逆に値上げ要求を聞いてもらえないなど、経営の頭痛の種にさえなりかねません。外部環境の変化に順応することが非常に重要ですが、それが出来ずに時間だけが経過している状況を根本的にかえていくことが必要なのではないかと考えるようになりました。
これに対しては、中小企業同士がもっと協力しあえる枠組みや行動が一つの策と考え、我々も独自でデータベースを基に様々な企業に直接手紙を書いて提案を始めています。思った以上に話を聞いてみたいという反応も多く、直接お伺いしたりWEBで面談をさせていただいたりしています。そこで中小企業の悩みはやはり共通する部分があるということに改めて気づかされました。今、事業承継、M&Aといった話は頻繁にされており、それを仲介する会社も日に日に増えている感があります。しかし、事業承継というのは後継者がいればできるといった単純な話ではありません。まるでものを売るように扱っている会社もあることに違和感を覚えています。まずは互いの信頼関係をつくり考え方の腹落ちをする時間も必要です。
ならば自分たちで課題を解決できるようにしていこうと考え、M&Aの一歩手前の解決策として、組合方式での協業促進システムをつくろうと考えました。手紙をおくることで新たに知り合った会社経営者に、じっくりと話をする時間をつくっていただき、徐々にこういった枠組みの話を進めています。
他社の経営者と一緒に困っている部分を重点的に解決し相互補完できる、ちょうどいいコスト感のシステムであれば、他社との協業も促進され、互いに企業価値を上げていくことができれば、ステークホルダーにとっても大きなメリットとなるはずです。
中小企業全体の底上げと活性化を可能するソリューション
協業によって他社との交流が生まれれば、社員の活性化も図れるのではないかと考えています。私も銀行で優秀な人たちと切磋琢磨してきた経験がありますが、中小企業はそういった機会もすくなく、自分の現在地を客観的にみるということはできません。競争や刺激を得る機会づくりも人を成長させる重要なことだと思います。中小企業にエネルギーがないのは人の成長が簡単に実現できないことも大きな要因だと思います。ものづくりを通じていろいろな企業と交流が促進されれば、社員の活躍の場、成長の場が広がることにもなると考えています。
今後は各社の課題をメニュー化して、組合価格で提供できるようなシステムを構築したいと思っています。弊社の事業領域を広げることにもつながりますし、より多くの方に協業のメリットを伝え、実際にソリューションを体験してもらいながら地域企業の意識を変え、中小企業全体の底上げをしたいという強い想いが根底にあります。企業や地域で働く多くの人たちが自分自身でしっかりと考え行動に移す意欲を喚起していかなければ、日本が抱える根本的な問題は解決しません。成長に踏み出す一歩として勇気を持ってもらえたらと思っています。
ツグナラ専門家による紹介
担当専門家:株式会社サクシード 株式会社サクシードの詳細

創業から100年以上の老舗企業。モーター分野での付加価値を高める経営戦略を実装しながら、自社成長だけでなく地域の中小企業同士での連携体を構築することで業界全体の活性化を促進することに取り組まれています。まさに地域を代表するツグナラ企業様です。
会社概要
| 社名 | 株式会社FEW |
| 創立年 | 1920年 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 仲下 正一 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| URL |
http://www.few.co.jp/index.html
|
| 本社住所 |
〒533-0031 |
| 事業内容 | ACモータ、トルクモー夕、ブラシ付DCモー夕、タコゼネ、ブラシレスDCモー夕、プリントモー夕、ロボットモータ及びモータ応用製品の製造・販売 |
| 事業エリア |
東京営業所 〒101-0045 |
|
名古屋営業所 〒456-0005 (株)安川メカトレック中部支社内 |

会社沿革
| 1920年 | 大阪市において個人商店として創業 |
| 1953年 | 安川電機製作所(現㈱安川電機)の出資を得て、資本金180万円により、現在地において㈱藤井精密回転機製作所を設立 |
| 1964年 | 資本金270万円に増資 |
| 1967年 | 資本金526.5万円に増資 |
| 1971年 | 資本金2,000万円に増資 |
| 1976年 | 資本金4,000万円に増資 |
| 1984年 | 直流モータの生産、販売の拡大 |
| 1985年 | 和歌山県橋本市に生産子会社日本エレクトリック㈱を設立(資本金1,000万円) ステータ巻線加工、アマチュア巻線加工及び製品組立 |
| 1987年 | 安川商事内に東京営業所開設 |
| 1993年 | 本社新社屋完成 |
| 1999年 | ブラシレスDCモータを事業化 |
| 2000年 | 本社所在地にて第2工場完成 |
| 2000年 | ㈱安川電機よりプリントモー夕、ロボットモータの生産受託があり製造開始 |
| 2002年 | 千代田区神田鍛冶町に東京営業所移転 |
| 2004年 | ISO 9001 : 2000認証取得 |
| 2004年 | ㈱安川電機よりプリントモータ、ロボッ卜モータの営業譲渡により弊社製品として販売拡大 |
| 2010年 | 創業90周年を迎える |
| 2010年 | ISO 9001 : 2008認証取得 |
| 2013年 | ㈱安川メカトレック中部支社内に名古屋営業所開設 |
| 2014年 | 本社隣地に倉庫用地(189平方メートル)購入 |
| 2015年 | 物流倉庫完成 |
| 2015年 | ㈱安川電機協力工場となる |
| 2016年 | エコアクション21認証取得 |
| 2017年 | SO9001:2015認証取得 |
| 2019年 | 大阪中小企業投資育成株式会社の資本参加を得る |
| 2022年 | ナントTSUNAGUファンド投資事業有限責任組合の資本参加を得る |
株式会社FEWの経営資源引継ぎ募集情報
事業引継ぎ
全国
モータ事業との協業・提携、相互発展を希望する事業者様を募集
- 募集地域
- 北海道 / 青森県 / 岩手県 / 秋田県 / 山形県 / 宮城県 / 福島県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県 / 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県 / 岐阜県 / 静岡県 / 愛知県 / 三重県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県 / 鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 山口県 / 徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県 / 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
- 募集業種
- 製造業 / 製造業(鉄鋼業) / 製造業(一般機械機器製造業) / 製造業(電気機器製造業) / 製造業(金属製品製造業) / 製造業(輸送機械器具製造業) / 製造業(精密機械製造業) / 製造業(その他)
人的資本引継ぎ
東京都
大阪府
新体制の100年企業で、ともに成長する仲間を募集中
公開日:2023/10/20
※本記事の内容および所属名称は2023年10月現在のものです。現在の情報とは異なる場合があります。
この企業を見た方はこれらのツグナラ企業も見ています
ツグナラ企業へのお問い合わせ
本フォームからのお問い合わせ内容はツグナラ運営事務局でお預かりし、有意義と判断した問い合わせのみツグナラ企業にお渡ししています。営業目的の問い合わせ、同一送信者による大量送付はお控えください。



