
笠間

引継ぎ実績あり
充実のひとときを味わうホテル・レストラン・宅配弁当の総合飲食企業
株式会社フードセンター
優れた戦略と効率化で家業を立て直し、新規事業で成長ステージへ
経営理念
挑戦を続け、価値を届け、未来を創造する
代表者メッセージ

弊社は、祖父の代に設立された本間兄弟商会での小売業からスタートしました。
その後、株式会社フードセンターとして分社し、笠間市初のスーパーマーケットをはじめ、不動産部門、笠間稲荷神社参道での土産店、ホテルと併設レストランの運営により、市内外のお客様の日常と大切なひと時を、おもてなしの心でお迎えしてまいりました。
地元の皆様に長年ご愛顧いただいている弊社だからこそ、お届けできるサービスがあると思っております。
今後も、ご年配の方からお子様、女性、男性などお客様層に合う、あらゆるニーズにお応えしてまいります。
代表 本間 雄一郎

私たちのこだわり
小売業からホテル・レストランのノウハウを活かし宅配弁当事業へ
株式会社フードセンターは、私の祖父が1963年に創業しました。茨城県笠間市で初となるスーパーマーケットの店舗を開業し、創業当初からかなり繁盛していたと聞いています。弊社はスーパーで得た利益をもとに不動産業や土産物店などを新たに立ち上げ、徐々に事業を多角化していきました。しかし競合店が増え、大手スーパーチェーンが笠間市に進出したことにより、スーパーマーケット事業からは撤退し、縁あって引き継いだ笠間市内のホテルと併設レストランを、メインの柱として事業を展開しています。
コロナ禍を経た現在では、レストラン内で製造する弁当宅配事業が弊社の新たな事業に加わりました。
ルーツは戦後の復興期に兄弟で立ち上げた本間兄弟商会
弊社の前身といえるのが、第二次世界大戦後に祖父と祖父の兄が立ち上げた「本間兄弟商会」です。祖父は7人兄弟のうち4番目で、戦後の貧しい時期を生き抜き家族を養うために、戦地から生きて戻った年の離れた祖父の兄とともに事業を立ち上げたそうです。
事業として選んだのは、戦後になり製造が盛んになってきていたバイクや自動車の修理でしたが、部品の仕入れにはある程度の資金が必要であり、資金を稼ぐために露天商のような形でアイスキャンディーや納豆等を売り歩くようになりました。
主力事業の元手を稼ぐために始めた露店販売でしたが、売り子を雇い、ほかの食品も扱うようになり、次第に小売業として成長していきました。
小売により資金繰りがうまくいくようになってからは、自動車修理事業も軌道に乗りはじめ、それを機に、本間兄弟商会の2事業のうち自動車部門は祖父の兄が株式会社本間商事として束ね、小売部門は株式会社フードセンターとして分社し祖父が経営することになりました。
他社スーパーの参入を見込み不動産業・土産物店へと手を広げる
祖父は1963年に会社を立ち上げると共に、小売のノウハウを活かしスーパーマーケットを開業しました。笠間市初のスーパーということもあり、創業直後から大盛況だったそうです。当初は競争相手もおらず独占市場でしたが、青果や生鮮食品などは時期によって生産や仕入れ量などが異なり原価の浮き沈みがあるため、祖父は好調な売上が続く中でも第2の柱となる事業を模索し始めました。
そして創業から7年後の1970年には不動産部門を立ち上げ、より経営が安定するよう、スーパーマーケットでの利益を不動産投資に充てていきました。
また、1986年には笠間稲荷神社の参拝客をターゲットとした土産物店も立ち上げます。笠間稲荷神社は日本三大稲荷のひとつとして親しまれ、現在でも年間350万人を超える参拝客が訪れるそうですが、当時は今以上の賑わいで土産店は相当な売上だったそうです。
不動産・土産物店・ホテル・レストランに軸足を移す
祖父は当初、スーパーマーケットをチェーン展開して店舗を増やしていくという戦略を立てていたそうです。しかし3店舗目を新設しようとした矢先に、1店舗目で火事が発生し長期休業せざるを得ない事態が発生しました。
そして火災の修繕が終わり「よし、今度こそ」と再び挑もうとしたところ、今度は祖父の息子、つまり私の父が25歳のときに倒れ、長期にわたり入院することになってしまいました。幸い父は回復しましたが、事業を拡大しようとする度に不運が重なったため、祖父はスーパー事業の拡大を断念したそうです。
そのうち、祖父が懸念していた通りスーパーマーケットの競合店が増え、売り上げが落ち始めました。しばらくはスーパー部門を維持していましたが、全国規模の大手スーパーチェーンが笠間市に進出したのを機に、1998年にスーパーマーケット事業から撤退しました。
祖父は不動産業と土産物店に事業を絞り、2001年には笠間稲荷神社の参道に2店舗目となる土産店「ほんまや」を新設しています。撤退したスーパーの店舗跡地は、テナントとして貸し出すことで不足した売上の埋め合わせを図りました。スーパーを撤退した時点では不動産収入があったので、資金を温存できれば事業拡大や新事業展開も望める状態ではありました。
ところが、2004年に異業種のホテルとホテル併設のレストランを引き継いでからは、経営の雲行きが怪しくなっていきました。このホテルとレストランは、設立から3年で債務超過となり倒産した物件で、前経営者は遠戚にあたる方だったことから、祖父は人助けのような形で引き継ぎを決めたようでした。しかし笠間市内の宿泊関連業は、2000年頃に北関東自動車道が開通してからは需要が低迷しており、多角化のタイミングとしてはあまり良くない状況でした。
家業の承継と「企業」への成長を意識し自らの力を磨く
3代目の私は、弊社がまだスーパーを運営していたころに生まれました。祖父の期待を一身に受けて育ち、幼少期にはすでに家業を継ぐことを意識し、幼稚園の卒園アルバムには「家を継いで社長になる」と書いていました。小中高に進学しても気持ちがぶれることはなく、東京の大学に進学した後も、卒業後は「家業」を「企業」にしようという意気込みでいました。
一方で、社会経験のないまま家業に戻っても、会社を成長に導けるほどの器量はなかなか身につかないだろうと思うようになり、就職活動の時期には、一度大きな企業で会社組織を学び自分の力を磨く必要があると考えました。
そして家業の承継を前提として業種や職種を絞り込んでいったところ、どのような業種業態でも必要とされ応用できる、Webコンサルティングが適しているだろうと思い至りました。家業ではかつて主事業としていたスーパーから撤退しましたが、祖父がリスクヘッジとして据えた不動産業の柱があったからこそ経営を継続できました。今後の事業拡大を考えていく上では、周辺事業よりも、事業を発信し繋ぐハブのような職種が適していると思い、自分の意思で就職先を決めました。
祖父の死により経営未経験の父が2代目社長に
しかし、就職から3年が経ったころに祖父が亡くなってしまいました。祖父は決断力や行動力に優れた人でしたが、スーパーマーケットのチェーン展開時に父が若くして倒れた経験を長らく悔やんでおり、父には無理をさせたくないと思っていたようでした。そのため最期まで社長の座を父に譲らず、父は祖父からの引き継ぎや勉強の機会を得られないまま社長に就任することとなりました。
数字の見方や経営感覚は、実践を積まなければ理解しにくいものであり、一刻も早く家業に戻り、経営を支えたいと思いました。しかし、Webコンサルティングの仕事は1~2年の長期スパンの案件も多く、無責任にすべてを放り投げて帰るわけにもいきません。残務処理や引き継ぎを全て済ませて私が実家に戻るまでには、祖父が亡くなってからさらに3年の月日がかかりました。
ホテルとレストランへのテコ入れで経営を改善
私が戻ったころには、家業の経営状態はかなり悪化していました。赤字の主な要因は遠戚から引き継いだホテルとレストランで、経営権が弊社に移った後も、異業種であることを理由に前任に任せきりだったため、体制も風土も変わらず、負債が膨らみ続けていました。
また併設されているレストランの方は、祖父が亡くなるまで貸テナントとして別会社に入ってもらっていたので、会社としての負担はさほどなく済んでいました。ところが、テナントで入っていた企業が、撤退をしてしまい、その会社が、雇用していたスタッフも弊社が引き継ぐこととなり、本社直営となった分の経費負担がさらにのしかかることとなりました。
不動産業と土産物店の売上でかろうじて倒産せずに済んでいる状態でしたが、このままでは会社が潰れてしまいます。家業に戻った私がまず手を付けたのは、ホテルとレストランの赤字改善でした。
レストランは同業が多く、初期費用もランニングコストも他の飲食業より高額であるため、最も経営が難しいといわれる業種であり、宿泊業のホテルは多額の設備管理費がかかります。ホテルを実質的に経営していた方には累積赤字額を示し、これまでの経営を反省し改善するよう訴えかけ「指示に沿って改善していけば1年後には確実に利益も出る」と約束しました。
レストラン事業はどうしても席数に限界があり、弊社の場合はどんなにお客様が入ったとしても6~7割の稼働が最大値でした。そのためキャパシティに関わらず、ホテル併設のレストランならではの高級感あるメニューを活かせるプラスアルファの事業として、宅配弁当事業への拡大を検討し商品開発を始めました。
その上で業務効率化やサービス改善に地道に取り組んでいったところ、1年目には赤字を改善することができました。2019年には翌年3月からの宅配弁当のサービス開始が決まり、なんとか経営建て直しの目途がつくようになったので、ようやく再スタートできると思っていた矢先にやってきたのがコロナ禍でした。
コロナ禍を逆手にとり成功を収めたホテルプランと宅配弁当事業
接客業のホテルとレストランは、コロナ直後は開店休業の状態が続くこととなりました。コロナ感染拡大から最初の半年はなす術がなく、売上も昨年対比を割りましたが、それぞれ対策をうって対応し下半期以降はコロナ禍でも前年比約120%のペースで事業を成長させていくことができました。
ホテルでの対策としては「レベニューマネジメント」と「ダイナミックプライシング」の仕組みを導入しました。これは端的に言えば「繁忙期は高く」「閑散期は安く」価格を設定することで、仕組み自体はホテル業界や航空業界などで既に幅広く導入されています。
しかし、素人判断や競合他社との価格比較などに基づいたあいまいな基準での運用は、かえって客足が遠のく原因にもなりかねません。そのため弊社では旅館・ホテル専門の集客支援コンサルタントの力も借りて1から戦略を練り直し、宿泊プランや食事内容などのサービスをニーズや市場価値とマッチさせ、付加価値をつけた上で導入することにしました。
さらにWebサイト上のプロモーションを見直し、ホテルの写真もすべて撮り直しました。Web戦略は、私の前職での経験が活かされたと思います。レストラン事業では、かねてから商品開発をしていた宅配弁当を、ホテルのプランと組み合わせて部屋食として提供したところ、「レストランでの食事は避けたい」という需要にマッチしてお客様から大変喜ばれ、コロナ禍でも単価を落とさず売上を伸ばすことができました。その後、本格的に宅配弁当事業を開始したところ、客室で提供した弁当が既に認知され評判になっていたため、オープン初年度から驚異的な売上を達成することができました。
「マルチタスク」導入で業務効率化と労働環境を改善
経営改善のために取り入れたもう1つの施策としては、星野リゾートを参考にした「マルチタスク」があります。ホテル業にはフロント、調理、清掃など様々な業務がありますが、それぞれの持ち場が忙しくなる時間には波があります。それぞれの社員がフロントも調理も清掃もこなせるようになり、繁閑の波に合わせて人員を配置すれば、より少ない人数で効率的に業務を回すことができます。
現在、弊社ではアルバイト・パートも含めて約30名が働いていますが、体制を変えた当時は、私の経営改革や急激な変化を受け入れられずに辞めていった社員も少なくありません。そのため人手が足りないときもあり、私自身も率先して玉ねぎを刻んだりハンバーグを作ったりしました。私はそれまで調理の経験はほぼありませんでしたが、新しく雇った若い料理人に教えてもらい朝から晩まで料理をつくり続けていたところ、コースのディナーも作れるようになり、今では包丁さばきもプロ並みだと自負できるまでになりました。
現在の社員には、アルバイトから登用した人もいます。彼らは私が役職の差異なく必死に働く姿を見ていたので、マルチタスクにもすんなり馴染み、何事も速やかに取り組んでくれるので、ビジネスにもスピード感が生まれました。マルチタスクと聞くと、1人1人の社員に負荷がかかると思われることも多いのですが、私が入社する前と比べると、むしろ労働時間は短くなり休暇も増えました。
以前はあまり休みがありませんでしたが、現在では月8回の休みに加え、1年に数回は3~4連休を取ることを推進しています。弊社がスタッフのプライベートの時間を確保できるようにしているのは、従業員満足度がお客様へのサービスに直結しているからです。お客様がお金を払う以上の付加価値を感じ、リピートをしていただけるようなサービスは、スタッフにより提供されます。スタッフのプライベートの時間をしっかり確保し、充実した楽しい生活を送ることができれば、社員の顔が明るくなって職場での笑顔も増えます。すると同じ材料で同じ料理を作っても、不思議とお客様のアンケート結果が良くなっていくのです。
お客様は味だけを求めるのではなく、空間演出や接客なども含めた、総合的な体験を求めて足を運ぶのです。もう1度来たいと思ってもらうためには、何よりもまず社員がいい雰囲気で働ける環境を作ることが大事だということが、職場環境づくりでよくわかりました。
私の考えや理念の共有としては、社長就任前後は「居酒屋ミーティング」をしていました。3人ずつのグループに分かれて飲みに行き、目標達成のために改善が必要な課題を話し合いました。当時はまだ明確な理念はありませんでしたが、会社の成長を願う私の気持ちは伝わったと感じています。経営理念は2025年の正月前後にまとめ、スタッフへの共有をおこなうようになりました。
飲食業をメインに年商100億円とコングロマリット企業を目指す
私は2024年9月に3代目社長として就任し、現在は承継に向けて父との2人代表の体制をとっています。
現在の飲食業でのビジネスモデルは、「森のレストランMonomi」内に、宅配弁当の「食彩ARATA」、店内焙煎コーヒーのポップアップストア「十人十豆(じゅうにんとまめ)」といったブランドを抱えています。
宅配弁当もコーヒーも、レストランの付加価値を上げるための事業でしたが、今後は1店舗ずつ分離させ、最大化していきたいと思っています。そのほか、レストランでの人気メニューを提供する店を人口規模の大きな地域に1店舗設け、事業拡大の足がかりとしたいと思っています。常陸牛ステーキなどをメインに出店する場合は、単価が高いため30~40代をメインターゲットとし、ラーメンやカフェの業態の場合は20代が客層になると思っています。それぞれ立地や人口などからメニューを絞り込み、数店舗を展開していきたいと考えています。
近い将来には年商100億円、うち営業利益10%を達成したいという思いがあります。レストラン、飲食業を成長の柱として利益を確保し、それを原資に事業拡大やM&Aを進め、最終的には複数事業を特定エリアで展開するコングロマリット企業を目指す構想を掲げています。
笠間を起点として事業エリアを徐々に拡大し、同時に事業領域も拡大していきたいと考えています。拡大する領域は飲食業やその周辺事業で、例えば健康やフィットネス、美容などです。
宿泊業の拡大も視野に入れてはいますが、初期投資やランニングコストがかかるため、安定軌道に乗り維持費を確保できるまでになってから着手したいと思っています。
このビジョン達成に向けて、社員が笑顔で働ける環境を守りつつ、着実に会社を成長させていきたいというのが私の考えです。
小売業からホテル・レストランのノウハウを活かし宅配弁当事業へ
株式会社フードセンターは、私の祖父が1963年に創業しました。茨城県笠間市で初となるスーパーマーケットの店舗を開業し、創業当初からかなり繁盛していたと聞いています。弊社はスーパーで得た利益をもとに不動産業や土産物店などを新たに立ち上げ、徐々に事業を多角化していきました。しかし競合店が増え、大手スーパーチェーンが笠間市に進出したことにより、スーパーマーケット事業からは撤退し、縁あって引き継いだ笠間市内のホテルと併設レストランを、メインの柱として事業を展開しています。
コロナ禍を経た現在では、レストラン内で製造する弁当宅配事業が弊社の新たな事業に加わりました。
ルーツは戦後の復興期に兄弟で立ち上げた本間兄弟商会
弊社の前身といえるのが、第二次世界大戦後に祖父と祖父の兄が立ち上げた「本間兄弟商会」です。祖父は7人兄弟のうち4番目で、戦後の貧しい時期を生き抜き家族を養うために、戦地から生きて戻った年の離れた祖父の兄とともに事業を立ち上げたそうです。
事業として選んだのは、戦後になり製造が盛んになってきていたバイクや自動車の修理でしたが、部品の仕入れにはある程度の資金が必要であり、資金を稼ぐために露天商のような形でアイスキャンディーや納豆等を売り歩くようになりました。
主力事業の元手を稼ぐために始めた露店販売でしたが、売り子を雇い、ほかの食品も扱うようになり、次第に小売業として成長していきました。
小売により資金繰りがうまくいくようになってからは、自動車修理事業も軌道に乗りはじめ、それを機に、本間兄弟商会の2事業のうち自動車部門は祖父の兄が株式会社本間商事として束ね、小売部門は株式会社フードセンターとして分社し祖父が経営することになりました。
他社スーパーの参入を見込み不動産業・土産物店へと手を広げる
祖父は1963年に会社を立ち上げると共に、小売のノウハウを活かしスーパーマーケットを開業しました。笠間市初のスーパーということもあり、創業直後から大盛況だったそうです。当初は競争相手もおらず独占市場でしたが、青果や生鮮食品などは時期によって生産や仕入れ量などが異なり原価の浮き沈みがあるため、祖父は好調な売上が続く中でも第2の柱となる事業を模索し始めました。
そして創業から7年後の1970年には不動産部門を立ち上げ、より経営が安定するよう、スーパーマーケットでの利益を不動産投資に充てていきました。
また、1986年には笠間稲荷神社の参拝客をターゲットとした土産物店も立ち上げます。笠間稲荷神社は日本三大稲荷のひとつとして親しまれ、現在でも年間350万人を超える参拝客が訪れるそうですが、当時は今以上の賑わいで土産店は相当な売上だったそうです。
不動産・土産物店・ホテル・レストランに軸足を移す
祖父は当初、スーパーマーケットをチェーン展開して店舗を増やしていくという戦略を立てていたそうです。しかし3店舗目を新設しようとした矢先に、1店舗目で火事が発生し長期休業せざるを得ない事態が発生しました。
そして火災の修繕が終わり「よし、今度こそ」と再び挑もうとしたところ、今度は祖父の息子、つまり私の父が25歳のときに倒れ、長期にわたり入院することになってしまいました。幸い父は回復しましたが、事業を拡大しようとする度に不運が重なったため、祖父はスーパー事業の拡大を断念したそうです。
そのうち、祖父が懸念していた通りスーパーマーケットの競合店が増え、売り上げが落ち始めました。しばらくはスーパー部門を維持していましたが、全国規模の大手スーパーチェーンが笠間市に進出したのを機に、1998年にスーパーマーケット事業から撤退しました。
祖父は不動産業と土産物店に事業を絞り、2001年には笠間稲荷神社の参道に2店舗目となる土産店「ほんまや」を新設しています。撤退したスーパーの店舗跡地は、テナントとして貸し出すことで不足した売上の埋め合わせを図りました。スーパーを撤退した時点では不動産収入があったので、資金を温存できれば事業拡大や新事業展開も望める状態ではありました。
ところが、2004年に異業種のホテルとホテル併設のレストランを引き継いでからは、経営の雲行きが怪しくなっていきました。このホテルとレストランは、設立から3年で債務超過となり倒産した物件で、前経営者は遠戚にあたる方だったことから、祖父は人助けのような形で引き継ぎを決めたようでした。しかし笠間市内の宿泊関連業は、2000年頃に北関東自動車道が開通してからは需要が低迷しており、多角化のタイミングとしてはあまり良くない状況でした。
家業の承継と「企業」への成長を意識し自らの力を磨く
3代目の私は、弊社がまだスーパーを運営していたころに生まれました。祖父の期待を一身に受けて育ち、幼少期にはすでに家業を継ぐことを意識し、幼稚園の卒園アルバムには「家を継いで社長になる」と書いていました。小中高に進学しても気持ちがぶれることはなく、東京の大学に進学した後も、卒業後は「家業」を「企業」にしようという意気込みでいました。
一方で、社会経験のないまま家業に戻っても、会社を成長に導けるほどの器量はなかなか身につかないだろうと思うようになり、就職活動の時期には、一度大きな企業で会社組織を学び自分の力を磨く必要があると考えました。
そして家業の承継を前提として業種や職種を絞り込んでいったところ、どのような業種業態でも必要とされ応用できる、Webコンサルティングが適しているだろうと思い至りました。家業ではかつて主事業としていたスーパーから撤退しましたが、祖父がリスクヘッジとして据えた不動産業の柱があったからこそ経営を継続できました。今後の事業拡大を考えていく上では、周辺事業よりも、事業を発信し繋ぐハブのような職種が適していると思い、自分の意思で就職先を決めました。
祖父の死により経営未経験の父が2代目社長に
しかし、就職から3年が経ったころに祖父が亡くなってしまいました。祖父は決断力や行動力に優れた人でしたが、スーパーマーケットのチェーン展開時に父が若くして倒れた経験を長らく悔やんでおり、父には無理をさせたくないと思っていたようでした。そのため最期まで社長の座を父に譲らず、父は祖父からの引き継ぎや勉強の機会を得られないまま社長に就任することとなりました。
数字の見方や経営感覚は、実践を積まなければ理解しにくいものであり、一刻も早く家業に戻り、経営を支えたいと思いました。しかし、Webコンサルティングの仕事は1~2年の長期スパンの案件も多く、無責任にすべてを放り投げて帰るわけにもいきません。残務処理や引き継ぎを全て済ませて私が実家に戻るまでには、祖父が亡くなってからさらに3年の月日がかかりました。
ホテルとレストランへのテコ入れで経営を改善
私が戻ったころには、家業の経営状態はかなり悪化していました。赤字の主な要因は遠戚から引き継いだホテルとレストランで、経営権が弊社に移った後も、異業種であることを理由に前任に任せきりだったため、体制も風土も変わらず、負債が膨らみ続けていました。
また併設されているレストランの方は、祖父が亡くなるまで貸テナントとして別会社に入ってもらっていたので、会社としての負担はさほどなく済んでいました。ところが、テナントで入っていた企業が、撤退をしてしまい、その会社が、雇用していたスタッフも弊社が引き継ぐこととなり、本社直営となった分の経費負担がさらにのしかかることとなりました。
不動産業と土産物店の売上でかろうじて倒産せずに済んでいる状態でしたが、このままでは会社が潰れてしまいます。家業に戻った私がまず手を付けたのは、ホテルとレストランの赤字改善でした。
レストランは同業が多く、初期費用もランニングコストも他の飲食業より高額であるため、最も経営が難しいといわれる業種であり、宿泊業のホテルは多額の設備管理費がかかります。ホテルを実質的に経営していた方には累積赤字額を示し、これまでの経営を反省し改善するよう訴えかけ「指示に沿って改善していけば1年後には確実に利益も出る」と約束しました。
レストラン事業はどうしても席数に限界があり、弊社の場合はどんなにお客様が入ったとしても6~7割の稼働が最大値でした。そのためキャパシティに関わらず、ホテル併設のレストランならではの高級感あるメニューを活かせるプラスアルファの事業として、宅配弁当事業への拡大を検討し商品開発を始めました。
その上で業務効率化やサービス改善に地道に取り組んでいったところ、1年目には赤字を改善することができました。2019年には翌年3月からの宅配弁当のサービス開始が決まり、なんとか経営建て直しの目途がつくようになったので、ようやく再スタートできると思っていた矢先にやってきたのがコロナ禍でした。
コロナ禍を逆手にとり成功を収めたホテルプランと宅配弁当事業
接客業のホテルとレストランは、コロナ直後は開店休業の状態が続くこととなりました。コロナ感染拡大から最初の半年はなす術がなく、売上も昨年対比を割りましたが、それぞれ対策をうって対応し下半期以降はコロナ禍でも前年比約120%のペースで事業を成長させていくことができました。
ホテルでの対策としては「レベニューマネジメント」と「ダイナミックプライシング」の仕組みを導入しました。これは端的に言えば「繁忙期は高く」「閑散期は安く」価格を設定することで、仕組み自体はホテル業界や航空業界などで既に幅広く導入されています。
しかし、素人判断や競合他社との価格比較などに基づいたあいまいな基準での運用は、かえって客足が遠のく原因にもなりかねません。そのため弊社では旅館・ホテル専門の集客支援コンサルタントの力も借りて1から戦略を練り直し、宿泊プランや食事内容などのサービスをニーズや市場価値とマッチさせ、付加価値をつけた上で導入することにしました。
さらにWebサイト上のプロモーションを見直し、ホテルの写真もすべて撮り直しました。Web戦略は、私の前職での経験が活かされたと思います。レストラン事業では、かねてから商品開発をしていた宅配弁当を、ホテルのプランと組み合わせて部屋食として提供したところ、「レストランでの食事は避けたい」という需要にマッチしてお客様から大変喜ばれ、コロナ禍でも単価を落とさず売上を伸ばすことができました。その後、本格的に宅配弁当事業を開始したところ、客室で提供した弁当が既に認知され評判になっていたため、オープン初年度から驚異的な売上を達成することができました。
「マルチタスク」導入で業務効率化と労働環境を改善
経営改善のために取り入れたもう1つの施策としては、星野リゾートを参考にした「マルチタスク」があります。ホテル業にはフロント、調理、清掃など様々な業務がありますが、それぞれの持ち場が忙しくなる時間には波があります。それぞれの社員がフロントも調理も清掃もこなせるようになり、繁閑の波に合わせて人員を配置すれば、より少ない人数で効率的に業務を回すことができます。
現在、弊社ではアルバイト・パートも含めて約30名が働いていますが、体制を変えた当時は、私の経営改革や急激な変化を受け入れられずに辞めていった社員も少なくありません。そのため人手が足りないときもあり、私自身も率先して玉ねぎを刻んだりハンバーグを作ったりしました。私はそれまで調理の経験はほぼありませんでしたが、新しく雇った若い料理人に教えてもらい朝から晩まで料理をつくり続けていたところ、コースのディナーも作れるようになり、今では包丁さばきもプロ並みだと自負できるまでになりました。
現在の社員には、アルバイトから登用した人もいます。彼らは私が役職の差異なく必死に働く姿を見ていたので、マルチタスクにもすんなり馴染み、何事も速やかに取り組んでくれるので、ビジネスにもスピード感が生まれました。マルチタスクと聞くと、1人1人の社員に負荷がかかると思われることも多いのですが、私が入社する前と比べると、むしろ労働時間は短くなり休暇も増えました。
以前はあまり休みがありませんでしたが、現在では月8回の休みに加え、1年に数回は3~4連休を取ることを推進しています。弊社がスタッフのプライベートの時間を確保できるようにしているのは、従業員満足度がお客様へのサービスに直結しているからです。お客様がお金を払う以上の付加価値を感じ、リピートをしていただけるようなサービスは、スタッフにより提供されます。スタッフのプライベートの時間をしっかり確保し、充実した楽しい生活を送ることができれば、社員の顔が明るくなって職場での笑顔も増えます。すると同じ材料で同じ料理を作っても、不思議とお客様のアンケート結果が良くなっていくのです。
お客様は味だけを求めるのではなく、空間演出や接客なども含めた、総合的な体験を求めて足を運ぶのです。もう1度来たいと思ってもらうためには、何よりもまず社員がいい雰囲気で働ける環境を作ることが大事だということが、職場環境づくりでよくわかりました。
私の考えや理念の共有としては、社長就任前後は「居酒屋ミーティング」をしていました。3人ずつのグループに分かれて飲みに行き、目標達成のために改善が必要な課題を話し合いました。当時はまだ明確な理念はありませんでしたが、会社の成長を願う私の気持ちは伝わったと感じています。経営理念は2025年の正月前後にまとめ、スタッフへの共有をおこなうようになりました。
飲食業をメインに年商100億円とコングロマリット企業を目指す
私は2024年9月に3代目社長として就任し、現在は承継に向けて父との2人代表の体制をとっています。
現在の飲食業でのビジネスモデルは、「森のレストランMonomi」内に、宅配弁当の「食彩ARATA」、店内焙煎コーヒーのポップアップストア「十人十豆(じゅうにんとまめ)」といったブランドを抱えています。
宅配弁当もコーヒーも、レストランの付加価値を上げるための事業でしたが、今後は1店舗ずつ分離させ、最大化していきたいと思っています。そのほか、レストランでの人気メニューを提供する店を人口規模の大きな地域に1店舗設け、事業拡大の足がかりとしたいと思っています。常陸牛ステーキなどをメインに出店する場合は、単価が高いため30~40代をメインターゲットとし、ラーメンやカフェの業態の場合は20代が客層になると思っています。それぞれ立地や人口などからメニューを絞り込み、数店舗を展開していきたいと考えています。
近い将来には年商100億円、うち営業利益10%を達成したいという思いがあります。レストラン、飲食業を成長の柱として利益を確保し、それを原資に事業拡大やM&Aを進め、最終的には複数事業を特定エリアで展開するコングロマリット企業を目指す構想を掲げています。
笠間を起点として事業エリアを徐々に拡大し、同時に事業領域も拡大していきたいと考えています。拡大する領域は飲食業やその周辺事業で、例えば健康やフィットネス、美容などです。
宿泊業の拡大も視野に入れてはいますが、初期投資やランニングコストがかかるため、安定軌道に乗り維持費を確保できるまでになってから着手したいと思っています。
このビジョン達成に向けて、社員が笑顔で働ける環境を守りつつ、着実に会社を成長させていきたいというのが私の考えです。
会社概要
| 社名 | 株式会社フードセンター |
| 創立年 | 1963年 |
| 代表者名 | 代表 本間雄一郎 |
| 資本金 | 1400万円 |
| 本社住所 |
309-1611 茨城県笠間市笠間2517-1 |
| 事業内容 | ホテル運営 レストラン運営 不動産業 小売業 弁当・オードブルの仕出し・宅配事業 |
| URL |
https://ibaraki-bento.com/
|
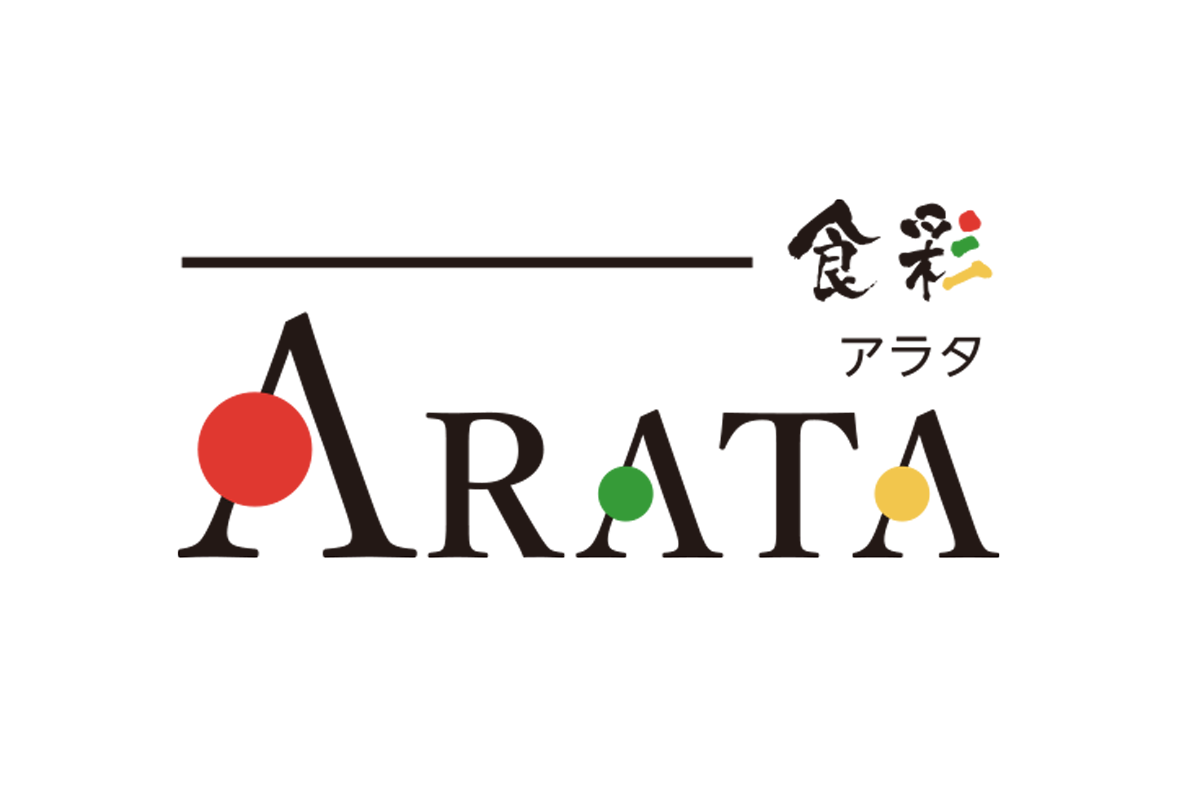

会社沿革
| 1963年 | 茨城県笠間市で設立、笠間市初のスーパーマーケットをオープン |
| 1970年 | 不動産部門を設立 |
| 1986年 | 土産物店を開業 |
| 1998年 | スーパーマーケット事業から撤退 |
| 2001年 | 土産物店の2号店として「ほんまや」開業 |
| 2004年 | ホテル イオ アルフェラッツを買収しホテル運営事業を開始 |
| 2013年 | ホテル イオ アルフェラッツ内のレストランを直営にし、レストラン事業として森のレストランMonomiを開始 |
| 2020年 | 食彩 ARATA(アラタ)オープン |
株式会社フードセンターの経営資源引継ぎ募集情報
公開日:2025/05/19
※本記事の内容および所属名称は2025年5月現在のものです。現在の情報とは異なる場合があります。



