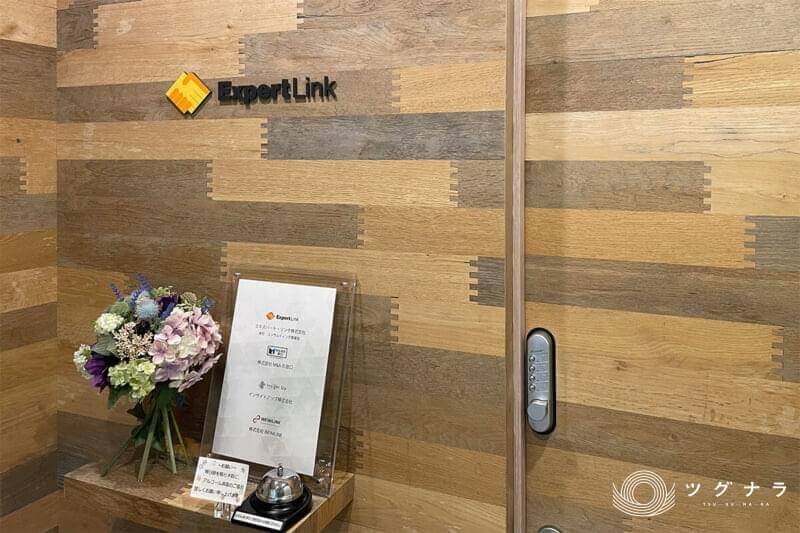奈良
奈良市
千代田区
「伝える」を「伝わる」に変え、次世代の情報発信を切り拓く
株式会社JITSUGYO
現場主義と戦略思考を武器に常に成長を希求する
経営理念
使命-MISSION-
「オールJITSUGYO」で、奈良や日本を活性化する
実現したいもの-VISION-
目指すは「伝わるべき人に伝わる世界」
提供価値-VALUE-
自分ごととして挑戦も結果も伴走する、長く深いお付き合いを
代表者メッセージ

私たちの使命は、単に情報を届けるのではなく「伝えるべき人に伝わる」コンテンツを創り出すことです。そのために、印刷だけでなく、Web・SNS・動画・アニメーションといった多様な手段を駆使しながら、プロフェッショナルとして、お客様の価値を最大限に引き出す情報発信を提供しています。
弊社は「お客様と共に挑戦し、伴走し続ける姿勢」を大切にしています。
どんな時代でも、企業が成長し続けるためには「変化」が必要です。変化は不安を伴うものですが、お客様の課題に深く向き合い、「ともに考え、ともに進む」私たちの姿勢は変わりません。
また、弊社は「紙」だけにとらわれない新たなステージへと進んでいます。 採用支援事業やデジタルマーケティングの領域に拡大し、企業や自治体の成長を後押しする情報戦略パートナーとしての役割を強化しています。
市場の変化に柔軟に対応しながら、情報発信の最前線をリードする存在であり続けます。
「JITSUGYOに頼めば間違いない」――そう言われる存在であるために、私たちは挑戦を止めません。「右肩上がりの成長」を実現するパートナーとして、これからも皆様とともに歩み続けます。
代表取締役 沢井 啓秀

私たちのこだわり
約70年前、成長産業であった印刷業で創業
弊社は、1954年に「沢井印刷所」として、私の祖父が創業しました。
もともと、祖父は地元の大手印刷会社で営業部長を務めていました。祖父は仕事に精力的に取り組んでおり、会社の売上の大半を一人で生み出していたと聞いています。
地域内で独立を考えますが、会社の稼ぎ頭であったことや、市場シェアの奪い合いとなるため難航してしまいます。しかし、主要銀行の頭取が「地域全体を盛り上げよう」と間を取り持ってくれ、祖父と工場担当の2名にて創業することができました。地域金融機関としての志が高い頭取とのご縁が弊社の誕生ルーツです。
創業時の日本は戦後の経済復興をとともに印刷業界も急速に拡大をしていた時代です。オフセット印刷の普及による印刷の効率性と品質の向上、また印刷機械の進化により大量の印刷物を短時間で生産できるようになりました。まさに技術革新と経済成長の相乗効果により現代のデジタル印刷技術の基盤を築いた時期でした。ただ、成長産業だからこその驕りのようなものが業界的にあったそうです。印刷業者が圧倒的有利な時代なため納期を守らず、価格を不当に吊り上げるなどモラルの低い同業者が多くいたようです。
そのような業者が多い中でも祖父は、「納期と品質を守る」ことを徹底していました。モラルの低い商売を行って一時的な利益が得られてもお客様の信頼を失ってしまっては一過性のビジネスにしかなりません。自社の実入り優先の商売ではなく、お客様のお役に立つことを優先とした商売をする、こういった想いや精神を大切にしていたようです。
その後、社名を「実業印刷」に変更します。祖父の代は小規模の会社で自宅兼工場の体制でしたが、父へ承継後、自宅と切り離しました。会社が組織化してスケールアップしているなと、幼いながらに私も感じていました。父の代も印刷業界は右肩上がりに伸びている時代で、「今後も伸び続けるだろう」と信じられていました。そのため、印刷業で成功している会社は、最新の機械を導入して急成長を目指す「設備投資ゲーム」の様相となっていたようです。
しかし、弊社は現状維持を貫き、無理な投資は積極的に行いませんでした。この時代の波に乗ることができず企業成長しきれなかったという反省点もありますが、過剰投資を防ぐことには繋がりました。
業界の最前線でからリーマン・ショックを機に家業へ
私は関西大学法学部を卒業後、東京都内にある印刷会社の株式会社帆風に就職しました。出版物の大部分が東京で発行されるため、家業を継ぐためには一番大きな市場でしっかりと勉強することで早く成長できると考えたからです。
仕事は多忙でしたが、同世代のメンバーも多く楽しくやりがいもあり、「このまま帆風で働き、出世していきたい」と思った時期もありました。しかし、帆風には地方の印刷会社の後継者も多くいたため、後継者のネットワークを構築することもできました。私より先に退職した仲間たちが家業を事業承継し、「東京で新規の仕事を獲得して、地方の工場に送る」ことで事業を拡大させていくのを目の当たりにしました。成功パターンを多く見ることで自分の中でも少しずつ承継後のイメージを描くことができました。
奈良の大手工作機械メーカーのマーケティング部門への出向も経験しました。2年間、動画制作やウェブ制作など、マーケティング分野のディレクションを担当しました。そんな折、リーマン・ショックが起き、広報物の制作はすべて中止されてしまいます。数か月にわたって仕事が全くない状態になり、ハードワークにやりがいを感じていた私にとって大きな衝撃でした。
「目的を持たないと、人間はこんなにも無力になるのか」と痛感していた矢先に、弊社の実業印刷も同じくリーマン・ショックの影響と急速に進んだデジタル化の波によって業績が悪化し始めたことを知りました。
自分の経験を活かして家業立て直したいと考えたことから2009年に実業印刷へ入社しました。
官へのサービス提供、低迷期から過去最高の売上へ
弊社を立て直すためにも、まずは現状把握が必要です。まずは業務の流れを理解するところからはじめました。工場に身を置き、指示書や仕様書を確認しながら、顧客の業種に基づいた受注内容を把握し、作業工程を目で見て理解していきました。その後は営業を担当するなど、徹底的に現場サイドから客観的に弊社を分析していきました。
この頃、ネット印刷が徐々に普及し始めており、特に中小企業や個人ユーザーにその利便性やコスト削減のメリットから利用されていました。顧客数の減少を防ぐためにも営業活動に注力しますが、本質的な解決には繋がらないとも感じていました。
私が弊社に入社した意味など改めて見つめ直していく中で、顧客層を変える決断をします。私には前職で培ってきたウェブサイトや動画を活用したプロモーション提案のノウハウがあります。そのノウハウと弊社の印刷技術を活用すれば現状打破出来ると考えました。ただ、このサービスの需要と供給の合点を模索すると、地域経済や地域住民の活動の活性化を目的に広報戦略を思案している自治体に顧客層をチェンジすることが必要だと判断しました。
過去に関係性のある自治体を中心に提案を行いました。そのような最中、地元の奈良県で広報活動の公募案件が開示され、結果受託することが出来ました。奈良の観光情報誌「ならり」などに携わりました。
民と官による売上構成比率に変えたことで売り上げも戻し、2年後の2011年には創業以来過去最高の売上を達成することが出来ました。事業内容の見直しなど抜本的な改革はリスクも伴いますが外部環境や内部環境をしっかり分析し課題整理を行えば、勝ち筋のある事業計画を立てることが出来ます。創業来弊社が攻めきれず躍進できなかったのは、成長産業として存在していた印刷業の環境に甘えていたためだと思います。もはや日本は時代が後押ししてくれるような国ではなくなりました。自らイノベーションを起こしていくことでしか企業成長はないのだと、この時強く体感することが出来ました。
その後、2014年に私が代表取締役に就任しました。と、同時に印刷会社だと印刷しかやっていない、プロダクトアウトの印象を与えてしまうので、マーケットインな考えであることをアピールするためにも社名を実業印刷から「JITSUGYO」へと変更しました。
人的資本経営を社内文化に取り入れる
代表に就任しましたが、プレイヤーとしての業務とマネジメント業務の両方を行っていました。新サービスなどビジネスモデルが変化していく渦中において、今までの弊社の歩み方との違いから現場ではストレスや反発が出てきます。これは至極当然のことだと思います。何かを変えようと思えば、そこにズレが少なからず生じます。そういったズレに現場レベルで気付けるためにもプレイヤーとして身を置き、ノウハウを共有しながら社員とコミュニケーションをとっていました。
しかし、会社の立て直しや新事業の確立に急ぎ過ぎたのか立て続けに退職者が出てしまいました。この頃の私は、プレイヤーではなく経営視点での発言が多く、社員の気持ちを汲み取ることが出来ていなかったと思います。
そのような中、経営の「やり方」ではなく「あり方」を学ぶ機会がありました。他の経営者の考えを知ったり、地域経営者のネットワークに参加したりしていくうちに、人的資本経営を知ることになります。人的資本経営とは、社員を企業の資産としてとらえ、成長を支援することによって企業の価値を最大化するという考えです。まさに、この考え方が私にも、弊社の文化としてもありませんでした。社員は人材ではなく人財なのだと、はっきり理解することができました。社員へ常に感謝する気持ちでコミュニケーションを取るよう私自身の意識を本質的に変えていきました。
また、社会保険労務士と連携しながら労働環境の整備を行い、人事評価制度や昇給制度を整えました。キャリアマップの策定も行い、随時バージョンアップを行っています。弊社としてどう社員に貢献するか、気持ちだけではなく制度としても示すことで「人財」なのだと考えを形にしました。
社員たちも自分の成長を喜び、実感することができるようになり、結果として生産性も向上しています。社員同士の助け合いの精神も築かれたように思います。若手社員や新卒の社員への育成の意識が生まれ、組織全体に一体感が生まれています。
2020年には経営理念を策定しました。それまで経営理念はなく、経営方針や行動指針を組織全体で共有する文化がありませんでした。策定の際には、まず営業や制作担当者にお客様を数人ずつ選んでもらい、「弊社を選んでくれる理由」について徹底的にヒアリングを実施しました。客観的な意見によって気づかされることも多々あり、「他社にはない弊社の強み」を理解することができました。その後、社員とともに、社内、お客様のニーズ、そして弊社への期待を反映した理念を策定しました。
「MISSION・VISION・VALUE」に落とし込み、まずは言語化することで弊社の在り方を皆が認識するところからはじめています。新しい事業を立ち上げる際や、イレギュラーな事態が発生した際は理念に基づいた行動をするなど、意思決定の指針として活用されています。
100年企業へ向けて未来を創る
現在の年間売上構成は広告事業部と採用支援事業部で3:1ですが、来期以降は採用支援事業をさらに拡大していきたい方針です。次なるステップである100年企業を目指すうえで、「伝わるべき人に伝わる」コンテンツ制作を事業の核としていきます。
弊社には、「ならり」の編集の際に培った、商品やサービスの魅力を最大限に引き出すためのノウハウがあります。お客様の目指す方向や、伝えるべき相手と伝えるべき情報を精査し、Webサイト、SNS、動画、アニメーション、紙媒体などの最適なツールで情報発信を行うことが可能です。
コンテンツ制作に重点を置くうえで、2020年からは新たに「採用革命®」という、採用に特化したアニメーション動画制作を行っています。
地域企業との関わりの中で、人手不足が加速し「若手社員の採用が困難になっている」との声があがっていることから、この課題を何とか解決したいと考えていました。
そこで、Z世代を対象とした採用で「選ばれる」ための、アニメーション動画制作を開始しました。企業の商品の魅力や経営者の考えをおよそ90秒のアニメーション動画にまとめています。現在、年間400本以上の企業の広報・営業用アニメーションを制作しています。私たちの情報発信力でお客様の採用活動やその先の業績を上げることができれば、地域の活性化につながると考えています。
今後も社会的課題解決に向けた取り組みを行い、奈良や日本が元気になるためのビジネスを展開していきます。また、地域内で印刷業者の廃業がたて続けに発生しています。紙媒体のマーケットは縮小傾向ではありますが、地域経済上に印刷業は必要です。弊社がその役割を担い続けていくためにも、永続企業として地域を牽引していきます。

約70年前、成長産業であった印刷業で創業
弊社は、1954年に「沢井印刷所」として、私の祖父が創業しました。
もともと、祖父は地元の大手印刷会社で営業部長を務めていました。祖父は仕事に精力的に取り組んでおり、会社の売上の大半を一人で生み出していたと聞いています。
地域内で独立を考えますが、会社の稼ぎ頭であったことや、市場シェアの奪い合いとなるため難航してしまいます。しかし、主要銀行の頭取が「地域全体を盛り上げよう」と間を取り持ってくれ、祖父と工場担当の2名にて創業することができました。地域金融機関としての志が高い頭取とのご縁が弊社の誕生ルーツです。
創業時の日本は戦後の経済復興をとともに印刷業界も急速に拡大をしていた時代です。オフセット印刷の普及による印刷の効率性と品質の向上、また印刷機械の進化により大量の印刷物を短時間で生産できるようになりました。まさに技術革新と経済成長の相乗効果により現代のデジタル印刷技術の基盤を築いた時期でした。ただ、成長産業だからこその驕りのようなものが業界的にあったそうです。印刷業者が圧倒的有利な時代なため納期を守らず、価格を不当に吊り上げるなどモラルの低い同業者が多くいたようです。
そのような業者が多い中でも祖父は、「納期と品質を守る」ことを徹底していました。モラルの低い商売を行って一時的な利益が得られてもお客様の信頼を失ってしまっては一過性のビジネスにしかなりません。自社の実入り優先の商売ではなく、お客様のお役に立つことを優先とした商売をする、こういった想いや精神を大切にしていたようです。
その後、社名を「実業印刷」に変更します。祖父の代は小規模の会社で自宅兼工場の体制でしたが、父へ承継後、自宅と切り離しました。会社が組織化してスケールアップしているなと、幼いながらに私も感じていました。父の代も印刷業界は右肩上がりに伸びている時代で、「今後も伸び続けるだろう」と信じられていました。そのため、印刷業で成功している会社は、最新の機械を導入して急成長を目指す「設備投資ゲーム」の様相となっていたようです。
しかし、弊社は現状維持を貫き、無理な投資は積極的に行いませんでした。この時代の波に乗ることができず企業成長しきれなかったという反省点もありますが、過剰投資を防ぐことには繋がりました。
業界の最前線でからリーマン・ショックを機に家業へ
私は関西大学法学部を卒業後、東京都内にある印刷会社の株式会社帆風に就職しました。出版物の大部分が東京で発行されるため、家業を継ぐためには一番大きな市場でしっかりと勉強することで早く成長できると考えたからです。
仕事は多忙でしたが、同世代のメンバーも多く楽しくやりがいもあり、「このまま帆風で働き、出世していきたい」と思った時期もありました。しかし、帆風には地方の印刷会社の後継者も多くいたため、後継者のネットワークを構築することもできました。私より先に退職した仲間たちが家業を事業承継し、「東京で新規の仕事を獲得して、地方の工場に送る」ことで事業を拡大させていくのを目の当たりにしました。成功パターンを多く見ることで自分の中でも少しずつ承継後のイメージを描くことができました。
奈良の大手工作機械メーカーのマーケティング部門への出向も経験しました。2年間、動画制作やウェブ制作など、マーケティング分野のディレクションを担当しました。そんな折、リーマン・ショックが起き、広報物の制作はすべて中止されてしまいます。数か月にわたって仕事が全くない状態になり、ハードワークにやりがいを感じていた私にとって大きな衝撃でした。
「目的を持たないと、人間はこんなにも無力になるのか」と痛感していた矢先に、弊社の実業印刷も同じくリーマン・ショックの影響と急速に進んだデジタル化の波によって業績が悪化し始めたことを知りました。
自分の経験を活かして家業立て直したいと考えたことから2009年に実業印刷へ入社しました。
官へのサービス提供、低迷期から過去最高の売上へ
弊社を立て直すためにも、まずは現状把握が必要です。まずは業務の流れを理解するところからはじめました。工場に身を置き、指示書や仕様書を確認しながら、顧客の業種に基づいた受注内容を把握し、作業工程を目で見て理解していきました。その後は営業を担当するなど、徹底的に現場サイドから客観的に弊社を分析していきました。
この頃、ネット印刷が徐々に普及し始めており、特に中小企業や個人ユーザーにその利便性やコスト削減のメリットから利用されていました。顧客数の減少を防ぐためにも営業活動に注力しますが、本質的な解決には繋がらないとも感じていました。
私が弊社に入社した意味など改めて見つめ直していく中で、顧客層を変える決断をします。私には前職で培ってきたウェブサイトや動画を活用したプロモーション提案のノウハウがあります。そのノウハウと弊社の印刷技術を活用すれば現状打破出来ると考えました。ただ、このサービスの需要と供給の合点を模索すると、地域経済や地域住民の活動の活性化を目的に広報戦略を思案している自治体に顧客層をチェンジすることが必要だと判断しました。
過去に関係性のある自治体を中心に提案を行いました。そのような最中、地元の奈良県で広報活動の公募案件が開示され、結果受託することが出来ました。奈良の観光情報誌「ならり」などに携わりました。
民と官による売上構成比率に変えたことで売り上げも戻し、2年後の2011年には創業以来過去最高の売上を達成することが出来ました。事業内容の見直しなど抜本的な改革はリスクも伴いますが外部環境や内部環境をしっかり分析し課題整理を行えば、勝ち筋のある事業計画を立てることが出来ます。創業来弊社が攻めきれず躍進できなかったのは、成長産業として存在していた印刷業の環境に甘えていたためだと思います。もはや日本は時代が後押ししてくれるような国ではなくなりました。自らイノベーションを起こしていくことでしか企業成長はないのだと、この時強く体感することが出来ました。
その後、2014年に私が代表取締役に就任しました。と、同時に印刷会社だと印刷しかやっていない、プロダクトアウトの印象を与えてしまうので、マーケットインな考えであることをアピールするためにも社名を実業印刷から「JITSUGYO」へと変更しました。
人的資本経営を社内文化に取り入れる
代表に就任しましたが、プレイヤーとしての業務とマネジメント業務の両方を行っていました。新サービスなどビジネスモデルが変化していく渦中において、今までの弊社の歩み方との違いから現場ではストレスや反発が出てきます。これは至極当然のことだと思います。何かを変えようと思えば、そこにズレが少なからず生じます。そういったズレに現場レベルで気付けるためにもプレイヤーとして身を置き、ノウハウを共有しながら社員とコミュニケーションをとっていました。
しかし、会社の立て直しや新事業の確立に急ぎ過ぎたのか立て続けに退職者が出てしまいました。この頃の私は、プレイヤーではなく経営視点での発言が多く、社員の気持ちを汲み取ることが出来ていなかったと思います。
そのような中、経営の「やり方」ではなく「あり方」を学ぶ機会がありました。他の経営者の考えを知ったり、地域経営者のネットワークに参加したりしていくうちに、人的資本経営を知ることになります。人的資本経営とは、社員を企業の資産としてとらえ、成長を支援することによって企業の価値を最大化するという考えです。まさに、この考え方が私にも、弊社の文化としてもありませんでした。社員は人材ではなく人財なのだと、はっきり理解することができました。社員へ常に感謝する気持ちでコミュニケーションを取るよう私自身の意識を本質的に変えていきました。
また、社会保険労務士と連携しながら労働環境の整備を行い、人事評価制度や昇給制度を整えました。キャリアマップの策定も行い、随時バージョンアップを行っています。弊社としてどう社員に貢献するか、気持ちだけではなく制度としても示すことで「人財」なのだと考えを形にしました。
社員たちも自分の成長を喜び、実感することができるようになり、結果として生産性も向上しています。社員同士の助け合いの精神も築かれたように思います。若手社員や新卒の社員への育成の意識が生まれ、組織全体に一体感が生まれています。
2020年には経営理念を策定しました。それまで経営理念はなく、経営方針や行動指針を組織全体で共有する文化がありませんでした。策定の際には、まず営業や制作担当者にお客様を数人ずつ選んでもらい、「弊社を選んでくれる理由」について徹底的にヒアリングを実施しました。客観的な意見によって気づかされることも多々あり、「他社にはない弊社の強み」を理解することができました。その後、社員とともに、社内、お客様のニーズ、そして弊社への期待を反映した理念を策定しました。
「MISSION・VISION・VALUE」に落とし込み、まずは言語化することで弊社の在り方を皆が認識するところからはじめています。新しい事業を立ち上げる際や、イレギュラーな事態が発生した際は理念に基づいた行動をするなど、意思決定の指針として活用されています。
100年企業へ向けて未来を創る
現在の年間売上構成は広告事業部と採用支援事業部で3:1ですが、来期以降は採用支援事業をさらに拡大していきたい方針です。次なるステップである100年企業を目指すうえで、「伝わるべき人に伝わる」コンテンツ制作を事業の核としていきます。
弊社には、「ならり」の編集の際に培った、商品やサービスの魅力を最大限に引き出すためのノウハウがあります。お客様の目指す方向や、伝えるべき相手と伝えるべき情報を精査し、Webサイト、SNS、動画、アニメーション、紙媒体などの最適なツールで情報発信を行うことが可能です。
コンテンツ制作に重点を置くうえで、2020年からは新たに「採用革命®」という、採用に特化したアニメーション動画制作を行っています。
地域企業との関わりの中で、人手不足が加速し「若手社員の採用が困難になっている」との声があがっていることから、この課題を何とか解決したいと考えていました。
そこで、Z世代を対象とした採用で「選ばれる」ための、アニメーション動画制作を開始しました。企業の商品の魅力や経営者の考えをおよそ90秒のアニメーション動画にまとめています。現在、年間400本以上の企業の広報・営業用アニメーションを制作しています。私たちの情報発信力でお客様の採用活動やその先の業績を上げることができれば、地域の活性化につながると考えています。
今後も社会的課題解決に向けた取り組みを行い、奈良や日本が元気になるためのビジネスを展開していきます。また、地域内で印刷業者の廃業がたて続けに発生しています。紙媒体のマーケットは縮小傾向ではありますが、地域経済上に印刷業は必要です。弊社がその役割を担い続けていくためにも、永続企業として地域を牽引していきます。

会社概要
| 社名 | 株式会社JITSUGYO |
| 創立年 | 1954年 |
| 代表者名 | 代表取締役 沢井 啓秀 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 事業エリア |
東京事務所
101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 |
| 本社住所 |
630-8144 奈良県奈良市東九条町6-6 |
| 事業内容 | 画・デザイン・取材・編集・印刷・広告・Webサイト制作・電子ブックポータルサイト「nara ebooks」・アニメーション動画「採用革命®」の運営 |
| URL |
https://www.jitsugyo.jp/
|


会社沿革
| 1954年 | 沢井印刷所創業 |
関連リンク
公開日:2025/03/24
※本記事の内容および所属名称は2025年3月現在のものです。現在の情報とは異なる場合があります。